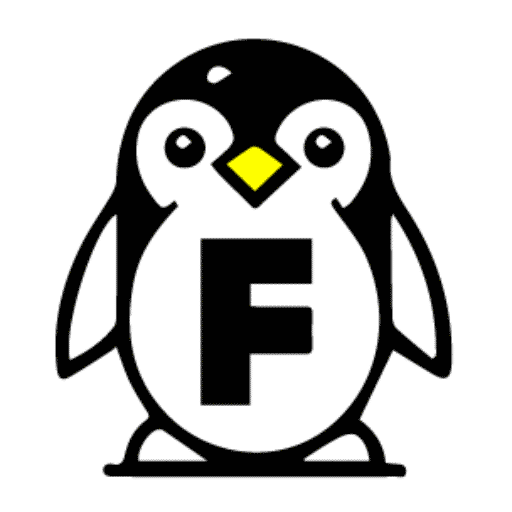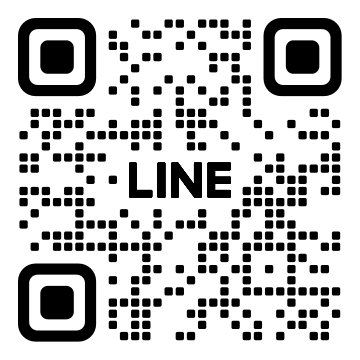なぜ今「研修動画制作」が注目されているのか?

近年、企業の人材育成や社員教育の方法が大きく変化しています。これまで多くの企業では、集合研修やOJT(On-the-Job Training)が主流でしたが、今「研修動画制作」が急速に注目されているのです。その背景にはいくつかの明確な理由があります。
1. コロナ禍で加速したオンライン研修のニーズ
2020年以降の新型コロナウイルスの影響で、対面の集合研修が難しくなり、企業は研修のオンライン化を迫られました。その結果、ZoomやTeamsなどのライブ配信型研修だけでなく、「動画によるオンデマンド研修」への注目が高まりました。動画であれば時間や場所に縛られず、受講者が自分のペースで学習できます。特に多拠点展開している企業や、シフト制の職場では非常に有効です。
2. 働き方改革と教育の効率化
働き方改革の影響で「長時間労働の是正」が求められるなか、社員教育に割ける時間も限られてきました。そこで、研修内容を動画にしておけば、必要なときに必要な内容をピンポイントで視聴でき、教育担当者の負担も軽減されます。一度作った動画は何度でも使えるため、教育の効率化とコスト削減を同時に実現できるのが大きな魅力です。
3. 教育の質を「均一化」できるメリット
社員研修でよくある問題のひとつが、教える人によって内容やクオリティにバラつきが出てしまうことです。しかし、動画であれば全員が同じ内容を、同じクオリティで学べます。これは、接客マナーや業務フロー、社内ルールなど、標準化が重要な研修において特に効果を発揮します。
4. 若手社員に馴染みやすい「動画文化」
今の若い世代、特に20代〜30代の社員にとって、「学び=動画」はごく自然な選択肢です。YouTubeやTikTokなどで日常的に動画コンテンツに触れている世代にとって、文字ばかりのマニュアルや長文のPDFは苦痛に感じることもあります。研修動画なら視覚的・聴覚的に伝えられるため、理解度も定着率も高まるのです。
5. 中小企業・個人事業主でも導入可能に
「動画制作なんてコストが高そう…」と思われがちですが、実は現在ではスマホやパワーポイント、無料の編集ソフトでも十分に研修動画は作れます。また、短時間・低価格で制作を請け負う外注サービスも増えており、費用対効果の高い投資として検討されるケースが増えています。
このように、「研修 動画 制作」は単なる流行ではなく、企業の教育戦略そのものを変える本質的な手段として、確実に定着しつつあるのです。
研修動画の主な種類と活用シーン

研修動画と一口にいっても、その内容や活用の仕方は多岐にわたります。目的に応じて適切な種類の動画を使い分けることで、教育効果を最大限に引き出すことができます。ここでは、企業でよく使われている研修動画の種類と、どのような場面で使われるのかをご紹介します。
オリエンテーション・新人研修向け動画
もっとも一般的なのが、新入社員やアルバイト向けのオリエンテーション動画です。企業理念、組織構成、就業ルール、社内マナーなど、すべての社員に共通して伝えるべき内容を映像化することで、入社直後の教育をスムーズに進めることができます。
また、配属前に一括で視聴させることで、教育担当者の工数も削減でき、離職防止にもつながります。これらは「顔の見える動画」にすることで親しみやすさも演出できます。
ハラスメント・コンプライアンス研修
セクハラやパワハラ、情報漏えいなど、今やどの企業でも避けては通れないのがコンプライアンス関連の研修です。これらは「一度きり」ではなく、年に1回以上の継続的な教育が求められる分野です。
動画にすることで、法改正に応じて柔軟に内容を更新したり、理解度チェックと連携させたりすることができます。また、感情に訴えるドラマ形式の研修動画も効果的です。
商品知識・サービスマニュアル動画
営業職や販売員向けに、自社の商品やサービスを深く理解させるための研修動画もよく使われています。特に、新商品発売時やキャンペーン開始時にタイムリーに情報を届けることが重要です。
マニュアル動画では、「正しい接客の流れ」「レジ操作」「電話応対」など、業務の手順を実演で示すことができ、紙のマニュアルよりもはるかに理解しやすくなります。
営業スキル・接客研修動画
トップセールスマンのロールプレイを収録した営業研修動画や、接客のポイントを解説する動画も人気です。こうしたコンテンツは「見て学ぶ」ことができるため、模倣学習に効果的です。
また、トークスクリプトの解説や、ケーススタディを交えた応用型の動画なども制作されており、受講者が具体的にイメージしやすい設計がされています。
スマホ・タブレット対応の研修動画
最近では、現場作業員やパートタイマーなど、PCを持たない従業員でも学べるように、スマートフォンやタブレットで視聴できる動画の需要が高まっています。特に建設、飲食、小売、介護などの業種では、「スキマ時間」に学べるモバイル対応動画が有効です。
短時間(3分〜10分程度)の「マイクロラーニング」形式が好まれ、業務の合間に繰り返し視聴することで定着率が向上します。
このように、研修動画には多様な種類があり、職種・目的・現場環境に合わせてカスタマイズすることで、より効果的な人材育成を実現できます。
研修動画制作の基本フロー【初心者向け】

「動画を使った研修が良いのは分かったけど、実際どうやって作ればいいのか分からない…」という声は少なくありません。ここでは、研修動画を初めて作る方でも取り組みやすいように、制作の基本的な流れを5つのステップで解説します。
1. 目的を明確にし、企画を立てる
まず大切なのは、「何のための研修なのか?」という目的を明確にすることです。例えば、
- 新人の離職を防ぐための社内理解向上
- ハラスメント対策のための全社員教育
- 業務の標準化を図るためのマニュアル化
目的が定まれば、伝えるべき内容やトーンも自然と決まります。ここで大まかな構成(動画の本数、長さ、テーマ)を決めておきましょう。
2. 台本(シナリオ)を作成する
動画のクオリティは、撮影や編集よりも「台本」で決まるといっても過言ではありません。視聴者が理解しやすく、かつ飽きずに見られるようにするには、
- 話す内容を箇条書きで整理する
- 1本の動画は5〜10分程度にする
- 視覚的に見せるパートと音声で伝えるパートを分けて設計する
といった工夫が必要です。最初はパワーポイントをベースにナレーションを当てるだけでも十分です。
3. 撮影(スマホでもOK)
機材はプロ仕様でなくても構いません。最近のスマートフォンであればフルHDの高画質撮影が可能です。重要なのは以下の3点です。
- 照明:逆光を避け、顔が明るく見えるように
- 音声:スマホの内蔵マイクでも可だが、可能なら外付けマイクを使用
- 構図:話す人が中央に来るように安定した撮影を
人物の登場が恥ずかしい場合は、スライド+音声だけの構成でも問題ありません。
4. 編集(無料ソフトから始められる)
撮影した動画は編集して整えることで、より伝わりやすくなります。初心者向けの無料編集ツールとしては、
- iMovie(Mac)
- Clipchamp(Windows)
- CanvaやPowerDirector(クラウド型)
などがあります。編集のポイントは、
- 不要な間をカットする
- テロップ(字幕)をつける
- BGMで雰囲気を和らげる
- 画面の切り替えで視聴者の集中力を保つ
など、視聴者の離脱を防ぐ工夫を入れることです。
5. 公開と共有の方法を整える
完成した動画は、視聴しやすい環境で配信することが大切です。一般的な方法は以下の通りです。
- 社内サーバーやGoogle Driveで共有
- YouTubeの限定公開で共有(外部非公開)
- eラーニングシステム(LMS)との連携
- 社内チャットツール(Slack、Teamsなど)でURLを通知
視聴後にアンケートやクイズを設けると、学習効果の測定も可能になります。
このように、特別なスキルがなくても、ステップを踏めば「伝わる」研修動画を作ることは十分に可能です。はじめは短い動画1本からでもOK。社内のナレッジを可視化することが、今後の教育資産になります。
自社制作と外注の違いと選び方
研修動画の導入を検討する際、必ず出てくるのが「自分たちで作るか、それとも外注するか?」という判断です。それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的や予算、人材リソースに応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
自社制作のメリットと注意点
メリット:
- 低コストで始められる:社内にスマホやPCがあれば、初期費用を抑えて制作可能。
- スピーディーに試せる:急な人事異動や新商品の説明など、必要なときにすぐ撮れる。
- 社内文化に合った表現ができる:社員が出演すれば親近感のある動画になりやすい。
注意点:
- クオリティにばらつきが出る可能性:照明、音声、構成などが不十分だと、視聴者の理解度に影響。
- 制作にかかる時間が見積もれない:台本作りや編集に思った以上の時間がかかる。
- 社内に「教え上手な人」がいないと難しい:話し手の伝え方で成果が変わる。
外注のメリットと注意点
メリット:
- プロの品質で印象がアップ:撮影・編集・ナレーションまでワンストップで対応してくれる会社が多い。
- 伝えたいことをロジカルに設計してくれる:構成から考えてもらえるため、情報が整理される。
- 視聴者の離脱を防ぐ演出が可能:動きやテンポ、アニメーションなど、見続けたくなる工夫が満載。
注意点:
- 費用が発生する:1本あたり5万〜30万円が相場(内容・尺・演出により異なる)。
- 修正のたびにやりとりが必要:スピード感に欠ける場合もある。
- 撮影に合わせたスケジュール調整が必要:社内の出演者や場所の確保など、準備が必要。
比較表:自社制作 vs 外注
| 比較項目 | 自社制作 | 外注制作 |
|---|---|---|
| コスト | ◎ 低コスト(ほぼ無料〜数千円) | △ 制作1本あたり数万円〜数十万円 |
| 時間 | △ 慣れれば早いが、最初は時間がかかる | ◯ スケジュールに沿って納品 |
| クオリティ | △ 個人差が出やすい | ◎ 一貫した高品質が期待できる |
| 柔軟性 | ◎ 思いついたらすぐ制作できる | △ 修正や追加には時間とコストがかかる |
| 社員の巻き込み | ◯ 社員出演で共感性アップ | △ 外注では演者が限られるケースも |
どちらを選ぶべきか?判断のポイント
- 予算に余裕がある場合:
→ 外注で一定の品質を確保し、台本作成や企画も任せるのが効率的。 - まず試してみたい場合:
→ 自社制作で短い動画を1本作り、反応を見てから外注検討。 - 一部だけ外注したい場合:
→ 台本と撮影は社内で、編集だけ外注というハイブリッド型も選択肢に。
どちらを選んでも大切なのは、「誰に・何を・どう伝えるか」を明確にすることです。最初から完璧を目指す必要はありません。小さく始めて、少しずつブラッシュアップしていくことで、自社にとって最適な研修動画の形が見えてきます。
研修動画の効果を最大化するポイント
ただ研修動画を作るだけでは、十分な教育効果を得ることはできません。視聴する側の集中力を維持し、理解を深め、行動変容に繋げるには「効果的な設計」が欠かせません。ここでは、研修動画の成果を最大限に引き出すための具体的なポイントを紹介します。
1. 見やすい映像、聞きやすい音声を意識する
教育コンテンツにおいて「視認性」と「聴き取りやすさ」は非常に重要です。たとえば、画面が暗くて表情が見えない、音声がこもっていて聞き取れない、といった動画は、内容がいかに素晴らしくても視聴者に届きません。
- 映像は明るく、背景をシンプルに
- 音声はできるだけマイクを使ってクリアに
- ノイズ(室外の音、エアコン音など)は事前に確認して排除
これらの点をおさえるだけで、動画の印象と伝達力は格段に上がります。
2. 最適な長さとテンポで構成する
研修動画のベストな長さは、1本あたり5〜10分程度が目安です。特にスマホ視聴が前提となる場合、20分以上の動画は途中離脱されるリスクが高くなります。
- 1本の動画につき1テーマに絞る
- 長い内容は複数本に分割(例:「前編・後編」など)
- テンポよく進め、間延びしないナレーションを意識する
短時間で「学びの核」を届ける設計が、記憶定着にもつながります。
3. テロップ・図解・アニメーションの活用
視覚的な補助は、理解度の向上に大きく貢献します。特に専門用語や抽象的な概念を扱う場面では、文字や図を加えるだけで「なるほど」と腑に落ちることが多いのです。
- キーワードや結論をテロップで表示
- 図や表をスライドに差し込む
- アニメーションで流れや因果関係を視覚化
CanvaやPowerPointでも十分な図解が可能なので、まずはシンプルな活用から始めてみましょう。
4. クイズやチェックリストで理解度を可視化する
見ただけで終わらせず、「ちゃんと理解できたかどうか」を確認することも重要です。これは動画による研修が「片方向」になりやすいことの対策にもなります。
- 動画の最後に簡単な確認クイズを挿入
- 視聴後に紙やGoogleフォームでミニテストを実施
- チェックリストで学んだ内容を実務で実践させる
教育効果を数値化できれば、社内でも動画導入の効果を説明しやすくなります。
5. LMSや配信プラットフォームの活用で継続的に管理
動画は作って終わりではありません。誰が見たのか、どこまで理解しているのか、継続的に管理することで、より深い教育施策へとつなげることが可能です。
- LMS(学習管理システム)で視聴履歴や成績を管理
- YouTubeの「限定公開」で再生数や視聴時間を確認
- 社内イントラと連携して進捗状況をレポート化
これらを活用することで、「作ったけど誰も見ていない」という事態を防ぎ、研修効果のPDCAを回すことができます。
このように、研修動画の効果を最大化するには、単なる映像制作にとどまらず、「視聴体験」「学習設計」「運用管理」の3軸で設計することが求められます。ちょっとした工夫を積み重ねることで、社員の理解度も、現場での実践率も確実に向上します。
よくある失敗例とその対策
「せっかく時間とお金をかけて研修動画を作ったのに、あまり活用されていない…」「思ったより効果が出なかった…」そんな声も少なくありません。ここでは、研修動画の導入・運用でよくある失敗パターンと、それぞれに対する具体的な対策を紹介します。
1. 動画が長すぎて最後まで見られない
失敗例:
30分を超える長尺の動画を一気に見せようとした結果、多くの社員が途中で離脱。アンケートの回収率も低く、効果が見えにくかった。
対策:
長い内容は必ず分割し、1本あたり5〜10分以内にまとめるのが鉄則です。複雑な内容も「ステップ1〜3」や「前編・後編」に分けるだけで視聴完了率が大幅に改善します。また、冒頭で「この動画で何が学べるか」を明確に伝えることで、視聴者の集中力を保つことができます。
2. 映像や音声のクオリティが低くて伝わらない
失敗例:
照明が暗く、声も聞き取りづらい状態で撮影された動画が配信され、「聞き取りにくい」「何を言っているのか分からない」といった不満が続出。
対策:
高価な機材を使わなくても、スマホ用三脚やLEDライト、外付けマイク(数千円)を使うだけで格段に改善します。また、撮影前に簡単なテスト録画を行い、映像と音声の状態を確認してから本番に臨みましょう。場合によってはナレーションだけ録音し、スライドやアニメーションと組み合わせる形式も有効です。
3. 内容が抽象的で「何をすればいいのか分からない」
失敗例:
理念や価値観ばかりを語る動画になってしまい、視聴者が「結局、何をすればいいの?」という状態に。
対策:
抽象的な話は具体的な事例やストーリーで補いましょう。「◯◯という場面で、こういう行動が求められる」というように、現場のリアルに即した例示を入れることで、理解と納得が深まります。また、動画の最後に「学んだことを明日からどう活かすか」を問いかけると、行動変容に繋がりやすくなります。
4. 一方通行の動画で学びが深まらない
失敗例:
ただ再生して終わりの動画が多く、視聴者が受け身になってしまい、理解度や記憶の定着が不十分。
対策:
動画の後に簡単な確認テストやクイズを設けるだけで、理解度を高めることができます。また、視聴後に「感想を共有するミーティング」や「チャットで質問を受け付ける場」を設けると、学びが深まるだけでなく、社内での会話も活性化します。
5. 社員の関与が得られず、動画が「見られない」まま放置される
失敗例:
せっかく動画を用意したのに、「忙しくて見ていない」「興味がわかない」といった理由で、視聴されないままになっている。
対策:
動画の導入は「現場巻き込み型」で進めるのが鉄則です。例えば、上司がまず見本として視聴・感想を共有することで部下も動きやすくなります。また、「◯日までに視聴と感想提出」といったスケジュール管理も重要です。さらに、動画内容に社員の登場シーンを入れると、自分事として受け止めやすくなります。
このような失敗は、誰でも一度は経験するものです。しかし、事前に原因と対策を理解しておくことで、無駄な時間やコストを削減し、研修動画の本来の価値を最大限に引き出すことができます。
成功事例:動画研修を導入して成果を出した企業とは?
「研修動画は本当に効果があるのか?」という疑問をお持ちの方のために、実際に動画研修を導入し、具体的な成果を上げた企業の成功事例をご紹介します。中小企業や個人事業主にも参考になるよう、予算・規模・目的が異なる3社のケースをピックアップしました。
【事例1】新人教育の効率化に成功した建設業A社
会社概要:
従業員数35名の建設業者。新入社員が毎年5~6名入社するが、現場ごとのOJTに任せていたため、教え方にバラつきがあり、離職率も高かった。
課題:
・毎年同じことを教える手間が非効率
・現場担当者によって教え方が違う
・ミスが続き、顧客満足度も低下
導入内容:
・「工具の使い方」「安全管理マニュアル」などの基礎動画を10本内製
・スマホで撮影、PowerPoint資料と音声を組み合わせて編集
・新入社員は入社初日にまとめて視聴+確認テストを実施
成果:
・新入社員の即戦力化までの期間が平均2週間短縮
・現場ミスが減少し、クレーム件数が前年比で半減
・教育係の社員からも「教える負担が軽くなった」と高評価
【事例2】マニュアル動画で業務品質が向上した美容院B社
会社概要:
美容院3店舗を展開する個人経営サロン。スタイリストの接客・技術の質を均一に保つことが課題だった。
課題:
・技術レベルの差により顧客満足度がバラついていた
・店長が毎回説明する時間が取れない
・新人スタッフがなかなか自信を持てない
導入内容:
・外注で「接客マナー」「電話対応」「シャンプー技術」の動画を各5分で制作
・スタッフルームのタブレットに常時視聴可能な状態で設置
・月1回の勉強会と連携して活用
成果:
・スタッフの自信がつき、口コミ評価が平均4.0→4.7に上昇
・新人教育の期間が1か月から2週間に短縮
・店長の指導時間を月10時間以上削減
【事例3】外注+LMS連携で教育コストを最適化した製造業C社
会社概要:
従業員120名の部品製造企業。新人・中堅・管理職と幅広い層への階層別研修が必要だった。
課題:
・紙のマニュアルが読まれず、内容も理解されにくい
・集合研修は業務を止めるため非効率
・教育記録が残らず、評価にも反映できない
導入内容:
・プロの動画制作会社に依頼して計30本の動画を制作
・LMSと連携し、視聴履歴や理解度テストのスコアを管理
・毎月の研修内容をデータ化し、評価制度に反映
成果:
・業務の停止時間が大幅に削減(集合研修に比べて月20時間以上)
・教育内容の標準化により、現場リーダーの育成が加速
・動画を資産化することで、今後の人材育成費用を半減予定
これらの事例から分かるように、研修動画の活用は業種や企業規模に関係なく効果を発揮します。ポイントは、「目的に合わせて適切な動画を作ること」「視聴しやすい仕組みを整えること」「現場の声を取り入れて改善を続けること」です。
特に中小企業にとっては、人的リソースが限られているからこそ、動画による“自動化された教育”が大きな武器になります。
これから研修動画を導入する企業へのアドバイス
「うちみたいな小さな会社でも研修動画って必要なんだろうか?」「そもそも何から始めればいいかわからない」――そんな疑問をお持ちの方は少なくありません。結論からいえば、どんな規模の企業でも、“最初の一歩”は小さくて構いません。大切なのは、社内の“伝える負担”を減らし、“教育の質”を一定に保つことです。
ここでは、これから研修動画の導入を検討する企業に向けて、具体的なアドバイスを5つの視点からお届けします。
1. まずは「内製の1本」から始めてみる
いきなり外注で高額な動画を依頼するのではなく、自分たちでスマホ1台で撮ってみることをおすすめします。例えば、
- 出社初日に見せたい社内ルール紹介
- よくある作業手順を動画で記録
- 社長やマネージャーからの一言メッセージ
これだけでも、社内に「動画で伝える文化」が生まれます。最初から完璧を目指すより、「とりあえずやってみる」ことで次に必要なことが見えてきます。
2. 社内に「動画編集が得意な人」がいなくてもOK
無料で使える動画編集ツール(例:Canva、CapCut、PowerDirectorなど)は、ドラッグ&ドロップで簡単に編集が可能です。また、ナレーションもスマホで録音した音声をそのまま使えます。
もし本格的な編集が必要になったら、部分的に外注することも可能です。たとえば「編集だけ依頼する」「台本だけ作ってもらう」といった形式なら、コストも抑えられます。
3. スモールスタート+パッケージ化で効率UP
研修動画を一気に10本、20本作ろうとするのではなく、**1本5分の動画を3本セットにして“パッケージ化”**するのがおすすめです。
例:
- 「新入社員向け基本セット」
- 「ハラスメント防止パック」
- 「営業マナー3本立て」 など
視聴する側も目的別に選びやすくなり、社内展開がしやすくなります。
4. 動画を「コンテンツ資産」として捉える
1回使って終わりではなく、研修動画は**何度でも活用できる“資産”**です。特に以下のような場面で再利用できます。
- 新人教育のたびに繰り返し使用
- 店舗間・部署間で共有
- YouTubeの限定公開でリモートスタッフにも対応
作った動画はGoogle Driveや社内クラウドで保管し、リンク1つで社内配信する仕組みを整えておきましょう。
5. 社員のリアクションを「改善のヒント」に変える
動画を導入したら、社員からの反応を必ず聞きましょう。「長い」「声が小さい」「もっと図がほしい」などのフィードバックは、次回以降の改善にとって何よりのヒントになります。
社内アンケートやSlackでの簡単なリアクション投稿など、意見を気軽に出せる場をつくっておくことがポイントです。
小さく始めて、大きな成果へ
研修動画は、「作る」ことよりも「活用し続ける」ことの方が大切です。まずは小さな一歩として、日常の業務を動画で記録してみる。社員に見てもらい、反応を確認する。それを繰り返すうちに、自然と自社に合った研修動画の形が見えてくるはずです。
「時間がない」「人手が足りない」――だからこそ、動画を使って伝える時間と手間を効率化し、未来の“人づくり”に投資していきましょう。
参考関連記事
集客に悩むあなたのクリニックを地域で一番に! |業界・業種別マーケティング戦略
クリニックの未来を切り開く、画期的なマーケティングソリューション。 あなたのクリニックや病院や歯科医院が直面している最大の課題は何ですか? 集客の難しさ、競合との差別化、あるいは地域社会での認知度の不足でしょうか。 わた […]
BtoB企業がYouTubeを活用して成果を上げるための完全ガイド|初心者でもわかる動画戦略入門
なぜ今、BtoB企業がYouTubeを活用すべきなのか? 「BtoB企業がYouTube? うちは一般消費者向けじゃないから関係ないよ」と思われる方もまだ多いかもしれません。ですが、今やBtoB企業こそYouTubeを活 […]
YouTubeチャンネル運営は内製がいい?外注がお得?
突然ですが、気になりませんか? 企業のYouTubeチャンネル運営において、自社で組織を構築して内製するのが良いのか、それとも外注にするほうが効率的なのか。この質問は、特に中小企業の経営者やマーケティングに慣れていない方 […]
採用動画・企業PR・ブランディング動画構成:誰でもわかる詳細版
1. ストーリー型 例:新人デザイナーの成長物語 導入: デザインに興味を持った主人公が、貴社に入社を決意するまでの葛藤と夢を描く 主人公の個性や強み、目標を具体的に描写し、視聴者の共感を呼ぶ 展開: 厳格な先輩デザイナ […]
DIAS|DigitalImpact AI Solutions
デジタル化の波に乗り遅れていませんか? 経営者や個人事業主の皆さん、SNSやAIの話題についていけず、ビジネスの成長が停滞していると感じていませんか? 毎日の業務に追われ、デジタルツールの使い方を […]
参考外部記事
中小企業庁:人材育成支援
└ 中小企業の教育支援施策を網羅した公式情報。補助金制度も紹介。
総務省|テレワーク研修導入事例
└ 動画研修を含むテレワーク導入に関する国の調査・支援情報。
YouTubeヘルプ:限定公開で社内動画共有
└ 限定公開設定を活用した社内研修動画の安全な共有方法を解説。
Udemy for Business
└ 企業向けの研修動画プラットフォームとして、社内教育のヒントになる。
LMSとは?比較と選び方(ボクシルマガジン)
└ LMS導入のメリットや動画活用との連携事例が学べる記事。
投稿者プロフィール

- 動画・映像マーケター・WEB集客・AI集客サポート
-
映像 × 生成AI × デジタルマーケティング
“伝える”だけでなく、“成果を生み出す”戦略的な映像マーケティングを。
13年以上にわたり、デジタルマーケティングコンサルタントとして
企業・店舗・士業・医療・観光など多様な業界の集客を支援。
外資系製薬会社、不動産・リフォーム会社、コンサルティング企業、
リスクマネジメント分野などで
広告運用・Googleアナリティクス解析・SEO/MEO対策を通じ、
継続的な集客導線とブランド成長に貢献してきました。
現在は、映像と生成AIを融合したマーケティング支援に注力。
YouTubeチャンネル運用、PR・採用・リクルート動画、動画広告、対談・インタビュー動画など、
戦略設計から撮影・編集・運用まで一貫してサポートしています。
撮影においては、被写体の魅力を最大限に引き出すために
カメラワーク・照明・音声のディレクションから、
必要に応じてドローン撮影なども組み合わせ、
表現力の高い映像を実現します。
また、生成AIを活用した台本制作・構成設計・SNS投稿文作成・分析自動化など、
AIによる効率化と創造性の両立を実現。
**「AI × 映像 × 集客設計」**の掛け合わせで、
これまでにない成果型の映像マーケティングを提供しています。
これまでに登録者150万人超のYouTubeビジネスチャンネル立ち上げに参画。
戦略構築・演出ディレクション・改善分析を担当し、
視聴維持率・エンゲージメント向上に貢献しました。
Yahoo!広告認定資格を保有し、10年以上の広告運用経験から、
**流行に左右されない「持続的な集客導線」**を設計します。
今の時代、動画は「映える」ためではなく、「動かす」ために使うもの。
データ・AI・映像表現を融合し、
企業の想いを“伝わるストーリー”として形にするパートナーであり続けます。
最新の投稿
 AI2025年11月29日AI時代に必須のスキル!成果を出すプロンプトの書き方【初心者向け基礎講座】
AI2025年11月29日AI時代に必須のスキル!成果を出すプロンプトの書き方【初心者向け基礎講座】 AI2025年11月11日【AI時代の集客術】GEOとSEOの違いとは?中小企業が今すぐすべき対策を徹底解説
AI2025年11月11日【AI時代の集客術】GEOとSEOの違いとは?中小企業が今すぐすべき対策を徹底解説 AI2025年11月1日YouTubeサムネイルイラスト用プロンプト完全ガイド
AI2025年11月1日YouTubeサムネイルイラスト用プロンプト完全ガイド AI2025年10月30日世界で使われるYouTube台本フォーミュラ10選
AI2025年10月30日世界で使われるYouTube台本フォーミュラ10選
LINEからのお問合せ
LINEからご予約の場合、下記内容をお書き添えくださいませ。
動画(撮影・編集・YouTube)に関すること
マーケティングやAIプロンプト設計 に関するご相談も承っております。
「オリジナルのChatGPTプロンプトを作りたい」「AI活用をビジネスに取り入れたい」なども、お気軽にご相談ください。
- あなたの現在の状態をできるだけ詳しくお聞かせください
- あなたのご要望を教えてください
- オンライン相談ご希望の有無
このほか マーケティング に関するあらゆるご相談も承っております。
\ 私が担当いたします /
代表 松井 要
14年以上のデジタルマーケティング経験を持ち、これまで多数の業界で成果を上げてきました。
350万人超の登録者を誇るYouTubeビジネスチャンネルの立ち上げにも参画し、戦略設計から運用まで幅広く支援。広告運用やSEO・MEO対策を通じて、多くのクライアントの集客課題を解決してきました。
現在は、映像制作やドローン空撮を活用したPR・集客支援にも注力。特に、インタビュー動画や施設紹介映像など「伝わるストーリー設計」によるブランディング支援を得意としています。
さらに、AIを活用したデータドリブンなマーケティング施策にも対応。業界や流行に左右されない、持続可能で成果の出る集客戦略をご提案します。
問い合わせフォームがいい人はこちらから