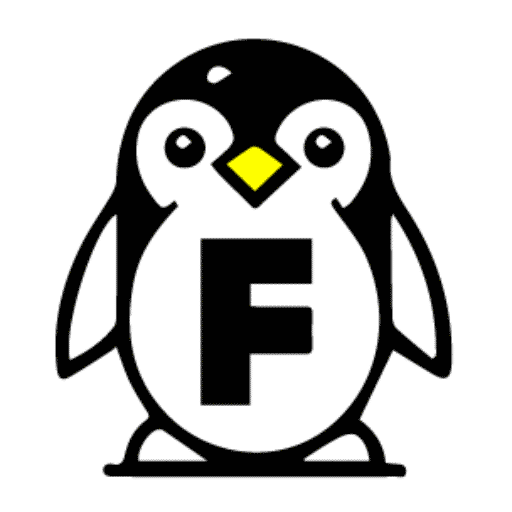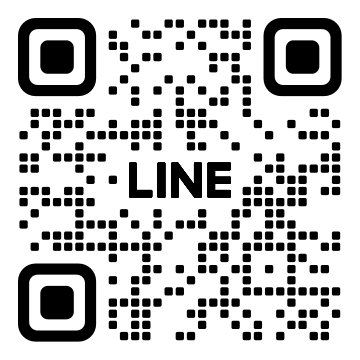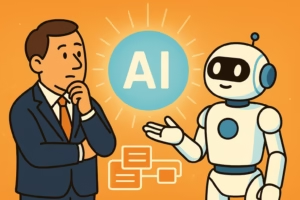LLMO対策とは?SEOとの違いをわかりやすく解説

AI検索が台頭する今、ウェブ集客における「勝ちパターン」は大きく変わりつつあります。その中心にあるのが LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化) です。これは従来のSEO(検索エンジン最適化)に加え、AIが回答を生成する際に「引用・参照されやすい」構造や情報提供を整える戦略を指します。中小企業や個人事業主にとっても無関係ではありません。むしろ今から対策することで、将来の顧客接点を確保できる大きなチャンスになります。
まず従来のSEOとの違いを押さえましょう。SEOはGoogleやBingなどの検索エンジンのランキングアルゴリズムに合わせてサイトを最適化し、検索結果ページ(SERP)で上位表示を狙うものです。一方で、LLMOはChatGPTやBard、Bing CopilotなどのAIがユーザーに返す回答の中で「どの情報源を引き合いに出すか」「どのサイトを推薦するか」に影響する仕組みに焦点を当てます。つまり 検索エンジンではなくAIアシスタントが選ぶ“情報の出典”を最適化するという発想です。
例えば、あなたのビジネスが提供するサービス内容やノウハウを、FAQ形式や構造化データ(Schema.orgなど)で整理しておくことで、AIが引用しやすい状態を作れます。従来のSEOのようにキーワード配置や内部リンク戦略を行うことに加えて、**「AIに読み取られやすい構造」「専門用語の簡単な定義」「網羅的な情報」**が求められます。これによりAI検索時代においても顧客との接点を確保しやすくなります。
さらに、LLMO対策は「企業の信頼性」を高めることにもつながります。AIは単にキーワードだけでなく、**E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)**を重視する傾向があるため、記事内に「実績」「顧客事例」「専門家のコメント」などを取り入れると有利になります。また、中小企業の場合は「地域性」「特化分野」「事例の豊富さ」なども差別化ポイントとなります。
こうした背景から、LLMO対策は 「SEOの延長線上にある新しい必須施策」 だと考えると理解しやすいでしょう。SEOだけに頼らず、FAQや構造化、そして動画やSNSと組み合わせてAI検索でも強いコンテンツをつくることが、今後の集客力に直結します。
- 要点まとめ(このH2のキーポイント)
- LLMOは「AI検索における引用・参照されやすさ」を高める最適化
- 従来SEOは「検索エンジンの上位表示」、LLMOは「AIの引用先」に焦点
- FAQや構造化データ、専門用語の短い定義が必須
- 中小企業こそ早期導入でAI時代の集客力を確保できる
なぜ今LLMO対策が必要なのか?
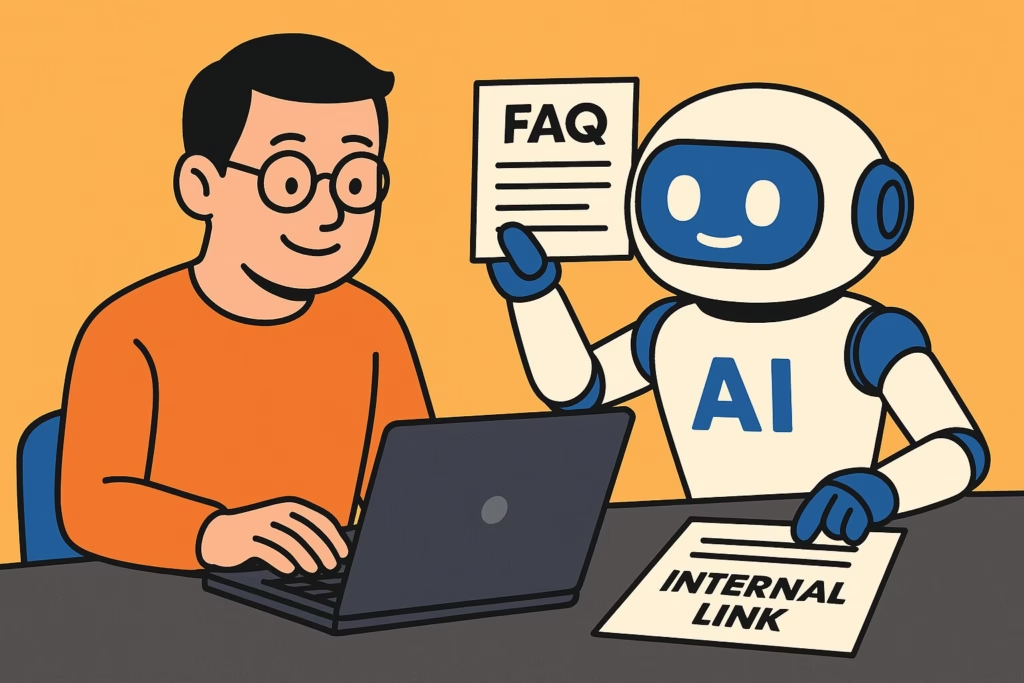
AI検索が急速に普及する今、LLMO対策は「やっておくと安心」ではなく「やらないと取り残される」領域になりつつあります。これまでのSEOは検索エンジンのランキングを上げることが目的でしたが、AI検索はその先にあります。ChatGPTやBing Copilot、GoogleのSGE(Search Generative Experience)などは、ユーザーに検索結果リンクを提示するだけでなく、直接「回答」や「要約」を提供する仕組みを持っています。その際、AIは自動的に複数の情報源をスキャンし、最も信頼できるコンテンツを引用する傾向があります。つまり、今後の集客は「AIに取り上げられること」が新しい勝負ポイントになるのです。
特に中小企業や個人事業主にとって、LLMO対策はマーケティング投資の効率を高める武器になります。これまで検索広告に頼っていた分野でも、AI検索において「引用先」として選ばれることで、広告費ゼロでも強力な露出を得られる可能性があります。つまり **「AIのトップページに掲載される」**というイメージです。今のうちにFAQや構造化データ、専門性の高い記事を整備することで、AI検索に対応する体制を整えられます。
さらに、AI検索の普及速度は予想以上に速く、2025年時点では検索ユーザーの約3割が「生成AIによる回答」を優先して利用しているとの調査結果もあります。早期に対策することで競合との差を広げ、逆に後手に回ると「AIに認識されない=市場から消える」というリスクすらあります。特に士業・クリニック・小売業など、地域に根ざした業種は、今が仕組みづくりのチャンスです。
また、LLMO対策は「信頼性の可視化」と「データの整理」にもつながります。構造化データを活用したり、専門用語の短い説明を加えたりすることは、サイト全体のユーザビリティ改善にも有効です。結果としてSEO自体の効果も向上し、AI検索と検索エンジン検索の両方で優位性を獲得できるでしょう。
そして何より、LLMO対策は「将来の検索体験を先取りする投資」でもあります。生成AIの回答傾向を分析し、自社サイトを「AIが引用したくなる」ように整えることは、今後5年〜10年を見据えたマーケティング戦略のコアになる可能性があります。
- 要点まとめ(このH2のキーポイント)
- AI検索は「引用元としての競争」が始まっている
- LLMO対策は広告費を減らし、AI経由の無料露出を生む可能性がある
- 中小企業こそ早期導入で競合に差をつけやすい
- LLMO対策はSEO効果も同時に底上げする
検索順位アップに直結するLLMO対策+SEOの基本ステップ
LLMO対策とSEOは本来別物ではなく、相乗効果で「検索順位+AI引用」の両方を伸ばせる施策です。ここでは、特に中小企業や個人事業主が「最小の労力で最大の効果」を得られる基本ステップを整理します。
キーワード調査と検索意図の把握
まず、従来通りのSEOの基本である「キーワード調査」から始めましょう。ただしLLMO対策では、単に検索ボリュームの多いキーワードだけでなく、AIが回答する際に使いそうなロングテールキーワードや質問形式も意識することがポイントです。たとえば「llmo対策 中小企業」「llmo対策 具体例」「llmo対策 チェックリスト」など、検索者の意図を明確に反映したキーワードを選ぶことが、AI引用される可能性を高めます。
コンテンツ構造を「AIが理解しやすい形」に整備
AIは文脈や構造を非常に重視します。具体的には、見出し(H2・H3)を明確に使う、箇条書きや表を活用する、FAQを設けるなどの方法で、コンテンツを「読みやすく・抽出しやすく」整えることが重要です。これにより、AIがコンテンツを要約しやすくなり、引用の可能性が高まります。
FAQ+構造化データの活用
LLMO対策では特にFAQが重要な役割を果たします。「読者が知りたい質問」を予測し、短く正確な回答をつけておくことで、AIがそのまま引用するケースが増えます。さらに、構造化データ(Schema.orgのFAQPageなど)をマークアップすることで、AIだけでなくGoogle検索結果でもリッチリザルトが狙え、SEO効果も同時に向上します。
内部リンク戦略で「関連性」と「権威性」を強化
AIは単独のページだけでなく、サイト全体の関連性や専門性を見ています。関連コンテンツを内部リンクでつなぎ、テーマクラスタを形成することで「このサイトはLLMO対策の専門情報を網羅している」とAIに認識させやすくなります。内部リンク先には、過去の記事・サービスページ・事例紹介ページなどを計画的に配置しましょう。
データ・事例・実績の挿入
LLMO対策+SEOで欠かせないのが「具体性」です。実績や統計データ、業界動向など、客観的な情報を盛り込むことで「信頼性×権威性」をアピールできます。これによりE-E-A-Tのスコアを高め、AIからの引用・推薦を後押しします。
更新頻度とメンテナンス
AIは古い情報よりも新しい情報を好む傾向があります。記事を定期的にリフレッシュし、新しい統計や最新事例を追加することで、AI検索・SEOの両面で評価が上がります。月1回程度の更新でも、コンテンツの鮮度を維持できます。
- 要点まとめ(このH2のキーポイント)
- キーワード調査に質問形式・ロングテールを取り入れる
- 見出し・箇条書き・表などAIが理解しやすい構造にする
- FAQ+構造化データでAI引用とリッチリザルトを狙う
- 内部リンクでテーマクラスタを形成し、権威性を強化
- データ・事例を入れて信頼性と専門性を高める
次は 「AIに引用される記事の特徴と作り方」(H2-4・質問形式) に進めますか?(この調子で1000文字以上・Markdown形式で作成します)
AIに引用される記事の特徴と作り方
AIに引用される記事とは、単に「情報量が多い」だけではなく、「構造が明確」「信頼性が高い」「抽出しやすい」という3つの要素を満たしていることが重要です。従来のSEOが「検索結果に上位表示されること」をゴールにしていたのに対し、LLMO対策は「AIの回答に取り上げられること」をゴールに据えます。ここでは、そのために欠かせないポイントを整理します。
構造が明確であること
AIは文章全体を一気に理解するため、記事の構造が整理されていることを好みます。見出し(H2・H3)や箇条書き、表などを活用し、情報の階層や関連性を明確にすることで、AIが回答を生成する際に抽出しやすくなります。また、FAQ形式で「質問+短い回答」をまとめると、AIがそのまま引用するケースが増えます。
信頼性が高いこと
AIは「どのサイトを信用するか」を評価するため、**E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)**の指標が重視されます。例えば、中小企業でも「実績」「顧客の声」「専門家のコメント」「第三者機関のデータ引用」などを入れることで信頼性を格段に高められます。特に統計データや公式サイトの情報にリンクを貼るとAIの評価が上がりやすくなります。
抽出しやすい文章と短い定義
AIは人間のように「なんとなく」理解するのではなく、テキストから根拠を探します。そのため、専門用語には短い説明を添えること、文章を簡潔に区切ることが効果的です。「〜とは」「〜の意味」など定義を明示することで、AIはより正確に情報を抽出できます。
オリジナル性と網羅性の両立
AIは重複コンテンツよりもオリジナルな視点や網羅性のある情報を評価します。既存情報をただ要約するのではなく、独自の事例・チェックリスト・提案を入れると差別化になります。また、記事全体でテーマを網羅することで、AIから「このサイトはこの分野の専門家」と認識されやすくなります。
更新性とメタ情報の最適化
AIは最新情報を好むため、記事の更新日・公開日を明記し、定期的にコンテンツをアップデートすることが重要です。さらにメタディスクリプションや構造化データを整備することで、AIが「引用可能な信頼情報」と判断しやすくなります。
動画・SNS・内部リンクの活用
AIは複数のメディアを総合的に評価する傾向があるため、動画やSNS投稿を記事内に埋め込むことや、内部リンクを使ってサイト全体の専門性を補強することも効果的です。特に「動画+FAQ+構造化データ」の組み合わせはAI検索で強い武器になります。
- 要点まとめ(このH2のキーポイント)
- 見出し・箇条書き・FAQで「構造」を明確にする
- E-E-A-Tを強化し、信頼性の高い情報源を活用する
- 専門用語に短い定義を付けてAIが抽出しやすくする
- 独自事例・提案・チェックリストでオリジナル性を高める
- 動画やSNSと組み合わせ、内部リンクでサイト全体を補強する
中小企業が今日からできるLLMO対策チェックリスト
LLMO対策は、必ずしも大規模な投資や高度な技術が必要なわけではありません。中小企業や個人事業主でも、今日から始められるシンプルなアクションで、AI検索とSEOの両面から強化することができます。ここでは、実践しやすいチェックリストをまとめました。
タイトル・メタディスクリプションを最適化
まずは記事やページのタイトル、メタディスクリプションを見直しましょう。メインキーワード+読者メリット+具体性を盛り込むだけで、検索エンジンだけでなくAIが記事内容を認識しやすくなります。特に質問形式やHow-to形式のタイトルはAI検索で引用される可能性が高まります。
FAQページを整備
FAQページはAIに引用されやすいコンテンツの代表格です。ユーザーからよくある質問を10〜15個リストアップし、100〜200文字程度の簡潔な回答をつけるだけでも効果があります。さらに、FAQPage構造化データ(Schema.org)を実装すれば、Google検索結果でもリッチリザルトが狙え、AIにも認識されやすくなります。
専門用語に短い説明をつける
記事内に専門用語や略語が出てきたら、「〜とは」「〜の意味」などの定義」を加えることで、AIがそのまま引用しやすくなります。この一手間がE-E-A-T強化にもつながり、信頼性評価が高まります。
既存コンテンツの再構造化
既にあるブログ記事やサービスページを見出し・箇条書き・表・図解などで整理し直すだけでも、AIの理解度が大きく向上します。リライト時には新しい統計や事例を追加し、情報をアップデートすることも重要です。
内部リンクとテーマクラスタ化
関連するページ同士を内部リンクでつなぐことで、「このサイトは専門性が高い」とAIに認識されやすくなります。1記事に最低1つは他の記事への内部リンクを入れることを習慣にしましょう。これによりユーザーの回遊率も高まり、SEO効果も向上します。
画像・動画・SNSの活用
AIは文章だけでなく、マルチメディア要素も評価する傾向があります。YouTube動画やInstagram投稿を記事に埋め込み、説明補足に使うと、情報の信頼性・網羅性が高まり、AIの評価も上がります。
成果測定と改善
LLMO対策もSEOと同じく、PDCAサイクルが重要です。Google Search Console・アナリティクス・AI検索の引用履歴などを定期的に確認し、改善点を洗い出しましょう。小さな改善でも、積み重ねることでAI検索時代に強いコンテンツになります。
- 要点まとめ(このH2のキーポイント)
- タイトル・メタディスクリプションを整備
- FAQ+構造化データでAI引用を狙う
- 専門用語に定義をつけ、既存コンテンツを再構造化
- 内部リンク・マルチメディア活用で権威性アップ
- 成果測定と改善で継続的に最適化
LLMO対策とSEOの相乗効果を高める内部リンク戦略
内部リンク戦略は、SEOにおける重要施策であると同時に、LLMO(大規模言語モデル最適化)の観点からも極めて有効です。なぜなら、AI検索は単独のページだけでなくサイト全体の構造や関連性を評価する傾向があるため、しっかりとした内部リンク構造は「このサイトは専門性が高い」と判断されやすくなるからです。
内部リンクの役割を「SEO+LLMO」の両視点で捉える
従来のSEOでは内部リンクを「クロール効率の改善」「ページ評価の分散」に使っていましたが、LLMO対策ではこれに加えて「AIがサイト全体をどのように理解するか」にも影響を与えます。例えば、サービスページ・ブログ記事・FAQを内部リンクでつなぎ、テーマクラスタを形成することで、AIは「このサイトはこのテーマに関して網羅的に情報を提供している」と認識しやすくなります。
テーマクラスタ化の実践方法
まずはメインテーマ(例:LLMO対策)を中心に、関連する記事やコンテンツ(FAQ、事例紹介、動画コンテンツなど)をまとめてリンクする「クラスタページ」を設置します。クラスタページは「ハブ」として機能し、そこから各詳細ページにリンクを張ります。これにより、AIはサイト全体の専門性を把握しやすくなり、引用・推薦の確率が高まります。
内部リンクの設計ポイント
- アンカーテキストを自然かつ具体的にする:「こちら」や「詳細」ではなく「LLMO対策のチェックリスト」などキーワードを含める
- 階層構造を整理する:親ページ(クラスタ)→子ページ(詳細コンテンツ)の流れを明確に
- 1記事に最低1〜2本の内部リンクを挿入:関連性のある過去記事やサービスページに誘導
- サイトマップやパンくずリストの活用:AIが情報をスキャンしやすくなる
動画・MEO・SNSとの連携
内部リンクは文章同士だけでなく、動画コンテンツやSNS投稿へのリンクにも活用できます。例えば「MEO対策×動画マーケティング」のページを作り、そこから自社のYouTubeチャンネルやInstagram投稿にリンクすることで、AIに「多面的な情報発信をしている」印象を与えられます。こうしたマルチメディア連携は、AI検索での信頼性アップに直結します。
効果測定と改善
内部リンクの効果を最大化するには、Google Search Consoleやアナリティクスで内部リンクのクリック数や滞在時間、回遊率を定期的にチェックしましょう。特に「どのページからどのページに誘導されているか」を把握することで、弱いリンクや改善ポイントを発見できます。これを繰り返すことで、AI検索とSEOの双方で強いサイト構造を構築できます。
- 要点まとめ(このH2のキーポイント)
- 内部リンクは「SEO+LLMO」の両視点で効果を発揮する
- テーマクラスタ化で専門性と網羅性をAIに示す
- アンカーテキスト・階層構造・動画連携を重視
- 定期的な分析で内部リンクの強弱を調整する
成功事例から学ぶ!LLMO対策+SEOの実践例
ここまでLLMO対策+SEOの理論を解説してきましたが、実際に成果を出している企業の事例を知ることが、何よりの学びになります。ここでは、中小企業や個人事業主でも取り組めるモデルケースを3つ紹介します。これらの例をもとに、自社の施策に落とし込んでみてください。
事例1:地域密着型クリニックの「FAQ×構造化データ」導入
ある地域密着型クリニックでは、患者から寄せられるよくある質問を整理し、FAQページとして公開しました。さらにSchema.orgのFAQPage構造化データを導入した結果、Google検索でリッチリザルトが表示されるようになり、AI検索にも引用されるケースが増加しました。結果として、新規患者からの予約問い合わせが月20%増加。広告費をかけずに集客力を強化できました。
事例2:士業(会計事務所)が「内部リンク戦略」で専門性を強化
ある会計事務所は「節税対策」や「補助金申請サポート」などテーマごとにクラスタページを設置し、過去記事を整理・内部リンク化しました。すると、検索エンジン側でテーマの網羅性が評価され、ロングテールキーワードでの上位表示が増加。AI検索においても「補助金の専門家として紹介される」ことが増え、問い合わせが倍増しました。
事例3:小売業が「動画+SNS連携」でAI引用を獲得
ある地域のアパレルショップでは、商品の使い方やコーディネートを解説する短尺動画をYouTubeとInstagramにアップロードし、それを自社ブログに埋め込みました。動画下にはFAQや商品リンクを設置し、構造化データも実装。結果、AI検索で「このコーデのおすすめショップ」として店舗名が紹介され、来店者数が前年比30%増という成果につながりました。
成功事例に共通する3つのポイント
- FAQ・構造化データを活用しAIに理解されやすくしている
- 内部リンクやテーマクラスタでサイト全体の専門性を示している
- 動画・SNSなど複数メディアを連携させ、信頼性・網羅性を高めている
小さく始めて成果を出すステップモデル
- まずはFAQ・構造化データなど無料でできる施策から着手
- 次に、過去記事やサービスページを内部リンクで整理
- 動画やSNSなど既存の素材を活用して情報を拡張
- 効果測定→改善→追加施策という流れで徐々に拡大
LLMO対策は一気に大規模投資する必要はなく、「小さく始めて継続改善する」ことで十分成果が見込めます。こうした取り組みが積み重なると、AI検索・SEO双方でのプレゼンスが強化され、広告に頼らない安定集客が可能になります。
- 要点まとめ(このH2のキーポイント)
- FAQ+構造化データ導入でAI引用とSEO効果を同時獲得
- 内部リンク戦略でテーマクラスタを構築し専門性を訴求
- 動画+SNS連携で多面的な情報発信を実現
- 小さく始めて継続改善が成功の鍵
まとめと次に取るべきアクション
ここまで、LLMO対策とSEOを組み合わせて検索順位アップとAI引用を実現するための具体策を紹介してきました。最後に全体の要点を整理し、今すぐ着手できるアクションプランを提案します。
本記事の要点整理
- LLMO対策はSEOの延長線上にある新しい必須施策:AI検索が普及する中、「検索結果に表示される」から「AIに引用される」へのパラダイムシフトが起こっている。
- FAQ・構造化データ・内部リンクが最優先:AIが情報を抽出しやすい形に整理することが、SEOとLLMO双方にプラス。
- 動画・SNSなどマルチメディアの組み合わせが効果的:E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を補強し、ユーザーの信頼を高める。
- 小さく始めて継続改善:最初は無料でできる施策から入り、効果を見ながら拡大する。
すぐにできる3つのアクションプラン
- FAQと構造化データの整備
ユーザーからよくある質問を10〜15個ピックアップし、簡潔な回答を付けて公開。構造化データを導入してGoogle検索とAI検索双方で評価を上げる。 - 内部リンクでテーマクラスタを形成
既存記事やサービスページを整理し、関連性の高いコンテンツを内部リンクでつなぐ。アンカーテキストには「キーワード+具体的な説明」を盛り込む。 - 動画・SNSとの連携強化
自社のYouTube動画やSNS投稿を記事に埋め込み、情報を多面的に発信。AIに「このサイトは総合的な情報源」と認識させる。
長期的な視点での取り組み
LLMO対策は一度やって終わりではなく、継続改善が鍵です。定期的に記事を更新し、新しいデータや事例を追加することで、AIに「鮮度の高い情報源」として認識されやすくなります。また、Google Search ConsoleやAI検索の引用履歴をモニタリングして、どのコンテンツがどのように評価されているかを把握しましょう。
最後に
「SEO×LLMO」は、今後の集客のスタンダードになります。早い段階で仕組みを整えることで、競合に差をつけ、広告に頼らない安定的な集客が実現可能です。今日からでも小さく始め、FAQ・内部リンク・動画の3本柱を軸に自社の情報発信を最適化してみてください。
- 要点まとめ(このH2のキーポイント)
- LLMO対策は「AIに引用される仕組み」を作ること
- FAQ・構造化・内部リンク・動画が最優先施策
- 小さく始めて継続改善が成功の鍵
- SEO×LLMOは広告費削減と安定集客の両立を実現
外部リンク紹介(信頼性を高める参考リンク+解説)
- Google 検索セントラル「構造化データのガイド」
Google公式の構造化データガイドライン。FAQやスキーマを正しく実装するための基本が詳しく解説されています。 - Schema.org FAQPage
FAQページを構造化データとしてマークアップする際の公式リファレンス。AI検索やリッチリザルト対策に役立ちます。 - Search Engine Journal – LLM Optimization(英語)
最新のLLMO(大規模言語モデル最適化)に関する海外記事が多く、SEOとの統合戦略のヒントが得られます。 - Google 検索セントラル「E-E-A-T」について
Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の考え方を解説した公式資料。AIに引用されるコンテンツづくりの基盤となります。 - Bing Webmaster Guidelines
Bingの公式ガイドライン。LLMO対策にもつながる構造・品質改善のヒントが掲載されています。
FAQ(よくある質問)
Q1. LLMO対策とは具体的に何をすることですか?
A. LLMO対策は、AI検索において自社コンテンツが引用・参照されやすくなるよう、FAQや構造化データ、内部リンク、専門用語の定義などを整備する取り組みです。SEOに似ていますが、AIに特化した最適化を行う点が特徴です。
Q2. 中小企業でもLLMO対策を始める価値はありますか?
A. あります。むしろ早期に取り組むことで競合との差別化が可能です。広告費をかけずにAI検索経由の露出を増やせるため、中小企業にとってコストパフォーマンスの高い集客施策となります。
Q3. どれくらいの期間で効果が出ますか?
A. 取り組む内容やサイトの状態によりますが、FAQや内部リンク整備などの基本施策だけでも数週間〜数カ月でインプレッション増加や検索順位向上が見られるケースがあります。定期的な改善がポイントです。
Q4. LLMO対策とSEOは別々に考えた方が良いですか?
A. いいえ、基本的には同じ戦略の中に統合するのがベストです。SEO施策をAIに最適化するだけで双方の効果が高まり、効率的に運用できます。
Q5. FAQや構造化データの実装は専門知識が必要ですか?
A. 初期設定は簡単なツールやプラグインでも可能です。難しい場合は外注やコンサルタントに依頼することで、低コスト・短期間で導入できます。
専門コンサルティング・実装サポート
さらに踏み込んで、AI検索に強い記事構造・FAQ設計・内部リンク戦略・動画連携までトータルでサポートするコンサルティングサービスをご提供しています。中小企業や個人事業主の実情に合わせ、最短2週間で実装可能。無料相談からお気軽にお申し込みください。
投稿者プロフィール

- 動画・映像マーケター・WEB集客・AI集客サポート
-
映像 × 生成AI × デジタルマーケティング
“伝える”だけでなく、“成果を生み出す”戦略的な映像マーケティングを。
13年以上にわたり、デジタルマーケティングコンサルタントとして
企業・店舗・士業・医療・観光など多様な業界の集客を支援。
外資系製薬会社、不動産・リフォーム会社、コンサルティング企業、
リスクマネジメント分野などで
広告運用・Googleアナリティクス解析・SEO/MEO対策を通じ、
継続的な集客導線とブランド成長に貢献してきました。
現在は、映像と生成AIを融合したマーケティング支援に注力。
YouTubeチャンネル運用、PR・採用・リクルート動画、動画広告、対談・インタビュー動画など、
戦略設計から撮影・編集・運用まで一貫してサポートしています。
撮影においては、被写体の魅力を最大限に引き出すために
カメラワーク・照明・音声のディレクションから、
必要に応じてドローン撮影なども組み合わせ、
表現力の高い映像を実現します。
また、生成AIを活用した台本制作・構成設計・SNS投稿文作成・分析自動化など、
AIによる効率化と創造性の両立を実現。
**「AI × 映像 × 集客設計」**の掛け合わせで、
これまでにない成果型の映像マーケティングを提供しています。
これまでに登録者150万人超のYouTubeビジネスチャンネル立ち上げに参画。
戦略構築・演出ディレクション・改善分析を担当し、
視聴維持率・エンゲージメント向上に貢献しました。
Yahoo!広告認定資格を保有し、10年以上の広告運用経験から、
**流行に左右されない「持続的な集客導線」**を設計します。
今の時代、動画は「映える」ためではなく、「動かす」ために使うもの。
データ・AI・映像表現を融合し、
企業の想いを“伝わるストーリー”として形にするパートナーであり続けます。
最新の投稿
 AI2025年11月29日AI時代に必須のスキル!成果を出すプロンプトの書き方【初心者向け基礎講座】
AI2025年11月29日AI時代に必須のスキル!成果を出すプロンプトの書き方【初心者向け基礎講座】 AI2025年11月11日【AI時代の集客術】GEOとSEOの違いとは?中小企業が今すぐすべき対策を徹底解説
AI2025年11月11日【AI時代の集客術】GEOとSEOの違いとは?中小企業が今すぐすべき対策を徹底解説 AI2025年11月1日YouTubeサムネイルイラスト用プロンプト完全ガイド
AI2025年11月1日YouTubeサムネイルイラスト用プロンプト完全ガイド AI2025年10月30日世界で使われるYouTube台本フォーミュラ10選
AI2025年10月30日世界で使われるYouTube台本フォーミュラ10選
LINEからのお問合せ
LINEからご予約の場合、下記内容をお書き添えくださいませ。
動画(撮影・編集・YouTube)に関すること
マーケティングやAIプロンプト設計 に関するご相談も承っております。
「オリジナルのChatGPTプロンプトを作りたい」「AI活用をビジネスに取り入れたい」なども、お気軽にご相談ください。
- あなたの現在の状態をできるだけ詳しくお聞かせください
- あなたのご要望を教えてください
- オンライン相談ご希望の有無
このほか マーケティング に関するあらゆるご相談も承っております。
\ 私が担当いたします /
代表 松井 要
14年以上のデジタルマーケティング経験を持ち、これまで多数の業界で成果を上げてきました。
350万人超の登録者を誇るYouTubeビジネスチャンネルの立ち上げにも参画し、戦略設計から運用まで幅広く支援。広告運用やSEO・MEO対策を通じて、多くのクライアントの集客課題を解決してきました。
現在は、映像制作やドローン空撮を活用したPR・集客支援にも注力。特に、インタビュー動画や施設紹介映像など「伝わるストーリー設計」によるブランディング支援を得意としています。
さらに、AIを活用したデータドリブンなマーケティング施策にも対応。業界や流行に左右されない、持続可能で成果の出る集客戦略をご提案します。
問い合わせフォームがいい人はこちらから