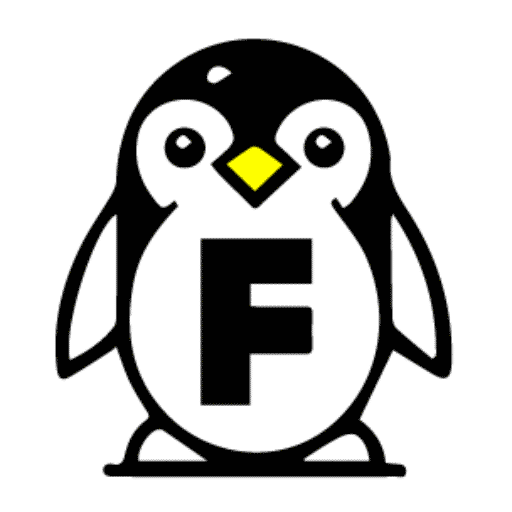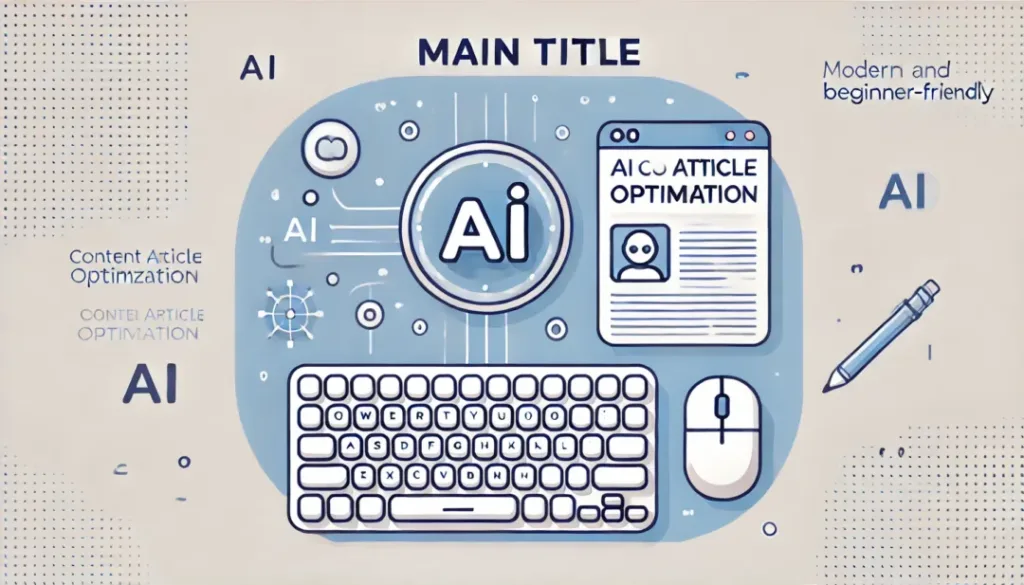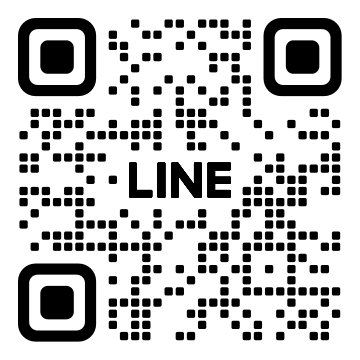SEOは本当にオワコンなのか?騒がれる理由とは

「SEOはもう終わった」「SEOはオワコン」といった言葉を、最近よく耳にするようになりました。実際に検索ボリュームを確認してみると、「seo オワコン」というキーワードはGoogleトレンドでも一定の関心を集めており、多くの経営者やマーケターがこのテーマについて関心を寄せています。
ではなぜ、今になって「SEOが終わった」と言われるようになったのでしょうか?
その背景には、テクノロジーの進化とユーザー行動の変化、そして検索エンジン側のアップデートが密接に関係しています。
理由①:Googleの検索結果の変化
まず大きな理由として、Googleの検索結果が大きく変化したことが挙げられます。
特に、以下のような変化がユーザーの混乱や不信感を生んでいます:
- 広告の増加: 上位4つが広告で埋め尽くされることも多く、本来のオーガニック検索が下に追いやられる。
- SGE(Search Generative Experience): 生成AIによる要約表示により、クリックせずに情報が完結してしまう。
- 検索意図のアルゴリズム変化: より文脈ベースの理解が進んでおり、単純なキーワード対策では順位が上がらない。
理由②:ユーザー行動の変化
以前は「何かを調べる=Google検索」でしたが、現在ではその構図が崩れつつあります。
| 行動 | 使われる媒体 |
|---|---|
| 商品やレビューの検索 | YouTube、Instagram、TikTok |
| 店舗の口コミ確認 | Googleマップ、食べログ、SNS |
| How To系の学習 | YouTube、ChatGPT、noteなど |
つまり、「Googleで検索される」こと自体が減っているのです。
これは中小企業にとっても影響が大きく、「SEOに力を入れても、検索されなければ意味がないのでは?」という疑問を生んでいます。
理由③:コンテンツの飽和と質の低下
SEOが注目されたここ10年、多くの企業や個人がコンテンツSEOに取り組みました。その結果、以下のような状況が生まれています:
- 検索上位に似たような記事が並ぶ(テンプレ化)
- AIライティングの普及により、質が伴わない記事が量産される
- 本当に必要な情報にたどり着きにくくなる
そのため、ユーザーから見ても「検索しても同じような記事ばかり」「結局役に立たなかった」と感じやすくなっています。
理由④:AIの台頭とChatGPTの登場
ChatGPTをはじめとする生成AIの登場は、SEOにとって強烈なインパクトを与えました。
とくに次のような使われ方が、SEOからの「離脱」を促進しています:
- 疑問の解消を検索ではなくAIに直接聞く行動パターン
- ブログ記事やサイトを経由せず、即答を得ることへの慣れ
- 企業側も「AIで答えを完結させる」スタイルへと移行し始めている
理由⑤:「SEO=面倒・時間がかかる」というイメージ
特に中小企業や個人事業主にとって、SEOは「すぐに効果が出ない」「何をすればいいかわかりにくい」という印象が根強くあります。
「SNSならすぐに反応があるけど、SEOは半年後とか…正直不安になる」
このような声も多く、より即効性が期待できるSNSや動画にマーケティングの軸を移す動きも見られます。
小まとめ:なぜ「オワコン」と言われるのか?
「SEO オワコン」という見方が広がっているのは、以下の複数の要因が重なった結果です:
- Googleの検索体験の変化
- ユーザーの情報取得スタイルの変化
- コンテンツの質に対する不満
- AIツールの台頭
- 中小企業が求めるスピード感とのギャップ
しかし、それは**「完全に終わった」ことを意味するのではありません**。
次の章では、検索エンジンの進化とユーザー行動の変化について、もう少し具体的に解説していきます。
検索エンジンの進化とユーザー行動の変化
SEOが「オワコン」と言われる背景には、検索エンジンそのものの進化と、それに伴うユーザーの情報取得スタイルの変化が密接に関係しています。この章では、特にGoogleの変化、ユーザーの検索習慣の変化、そして新たな検索手段の登場という3つの観点から解説していきます。
Googleの進化と「E-E-A-T」時代の到来
Googleはここ数年、従来のキーワード主義から、より“信頼できる情報”を評価する方向に大きく舵を切りました。その象徴が、以下の4つの評価基準である「E-E-A-T」です。
| 指標 | 意味 |
|---|---|
| Experience(経験) | 実体験に基づく情報か |
| Expertise(専門性) | 専門知識を持つ筆者か |
| Authoritativeness(権威性) | 業界内での信頼性があるか |
| Trustworthiness(信頼性) | 情報の正確さ・安全性があるか |
つまり、表面的なSEOテクニックではなく、**「誰が、どんな実体験を元に書いているか?」**が問われるようになってきたのです。
たとえば、
- 弁護士の書いた法律解説
- 美容師の書いた髪型アドバイス
- 地元の飲食店が発信するグルメ情報
などが、Googleにとって「価値あるコンテンツ」となり得ます。
「検索しない世代」の台頭
デジタルネイティブ世代、特にZ世代(1996年以降生まれ)は、**「Google検索を使わない」**という新たなスタイルを持っています。
✅ 情報源ランキング(Z世代)
1位:YouTube
2位:Instagram
3位:TikTok
4位:ChatGPT
5位:Google
これはつまり、「文字よりも動画」「一覧よりもおすすめ表示」「検索よりも対話的な体験」が求められているということ。
その結果、「Googleで調べてサイトを読んで理解する」というスタイルは相対的に減少しているのです。
SGE(Search Generative Experience)の登場
Googleが現在試験導入を進めている**SGE(生成AI検索体験)**は、今後の検索エンジンのあり方を根本から変える可能性があります。
- 検索結果の上部にAIが要約を提示
- 回答の中にリンクが複数含まれる
- ユーザーがクリックしなくても「答え」が手に入る
たとえば、「SEOの将来性」と検索したとき、これまでは複数のサイトを見て自分で答えを判断していましたが、SGEでは**「AIが要点をまとめて提示」**してくれるようになります。
このことは、「クリックされる回数そのものが減る」=SEOの難易度が上がることを意味します。
マルチモーダルな検索スタイル
ユーザーはもはや「テキスト検索」だけではありません。
| 検索スタイル | ツール・アプリ |
|---|---|
| 音声検索 | Siri, Google Assistant |
| 画像検索 | Google Lens, Pinterest |
| 動画検索 | YouTube, TikTok |
| AIチャット | ChatGPT, Claude, Gemini |
つまり、「SEO=Googleのテキスト検索に上位表示させること」という古い定義は、現代では通用しなくなってきているのです。
これからは**「情報が届く場所すべてが検索の対象」**という広義のSEO戦略が必要になります。
検索行動の変化にどう対応すべきか?
企業や個人がこの変化に対応するには、以下のような施策が有効です。
✅ 複数チャネルで情報発信する
- YouTubeやInstagramでコンテンツを展開
- 同じテーマを「動画」「ブログ」「SNS」で届ける
✅ E-E-A-Tをベースにしたコンテンツ強化
- 実名やプロフィールを明記
- 写真・動画・経験談を盛り込む
✅ 検索以外の流入も意識
- SNS経由、LINE公式、YouTube概要欄など、検索に依存しない導線を確保
小まとめ:SEOは「変化」に対応できるかどうか
検索エンジンは「進化」し、ユーザーは「行動」を変えています。
SEOが「終わった」のではなく、**「今までのやり方では通用しなくなった」**というのが、正確な捉え方でしょう。
次章では、**中小企業や士業・店舗経営者などにとっての「SEOの今と未来」**について、具体的な視点で解説します。

検索エンジンの進化とユーザー行動の変化
SEOが「オワコン」と言われる背景には、検索エンジンそのものの進化と、それに伴うユーザーの情報取得スタイルの変化が密接に関係しています。この章では、特にGoogleの変化、ユーザーの検索習慣の変化、そして新たな検索手段の登場という3つの観点から解説していきます。
Googleの進化と「E-E-A-T」時代の到来
Googleはここ数年、従来のキーワード主義から、より“信頼できる情報”を評価する方向に大きく舵を切りました。その象徴が、以下の4つの評価基準である「E-E-A-T」です。
| 指標 | 意味 |
|---|---|
| Experience(経験) | 実体験に基づく情報か |
| Expertise(専門性) | 専門知識を持つ筆者か |
| Authoritativeness(権威性) | 業界内での信頼性があるか |
| Trustworthiness(信頼性) | 情報の正確さ・安全性があるか |
つまり、表面的なSEOテクニックではなく、**「誰が、どんな実体験を元に書いているか?」**が問われるようになってきたのです。
たとえば、
- 弁護士の書いた法律解説
- 美容師の書いた髪型アドバイス
- 地元の飲食店が発信するグルメ情報
などが、Googleにとって「価値あるコンテンツ」となり得ます。
「検索しない世代」の台頭
デジタルネイティブ世代、特にZ世代(1996年以降生まれ)は、**「Google検索を使わない」**という新たなスタイルを持っています。
✅ 情報源ランキング(Z世代)
1位:YouTube
2位:Instagram
3位:TikTok
4位:ChatGPT
5位:Google
これはつまり、「文字よりも動画」「一覧よりもおすすめ表示」「検索よりも対話的な体験」が求められているということ。
その結果、「Googleで調べてサイトを読んで理解する」というスタイルは相対的に減少しているのです。
SGE(Search Generative Experience)の登場
Googleが現在試験導入を進めている**SGE(生成AI検索体験)**は、今後の検索エンジンのあり方を根本から変える可能性があります。
- 検索結果の上部にAIが要約を提示
- 回答の中にリンクが複数含まれる
- ユーザーがクリックしなくても「答え」が手に入る
たとえば、「SEOの将来性」と検索したとき、これまでは複数のサイトを見て自分で答えを判断していましたが、SGEでは**「AIが要点をまとめて提示」**してくれるようになります。
このことは、「クリックされる回数そのものが減る」=SEOの難易度が上がることを意味します。
マルチモーダルな検索スタイル
ユーザーはもはや「テキスト検索」だけではありません。
| 検索スタイル | ツール・アプリ |
|---|---|
| 音声検索 | Siri, Google Assistant |
| 画像検索 | Google Lens, Pinterest |
| 動画検索 | YouTube, TikTok |
| AIチャット | ChatGPT, Claude, Gemini |
つまり、「SEO=Googleのテキスト検索に上位表示させること」という古い定義は、現代では通用しなくなってきているのです。
これからは**「情報が届く場所すべてが検索の対象」**という広義のSEO戦略が必要になります。
検索行動の変化にどう対応すべきか?
企業や個人がこの変化に対応するには、以下のような施策が有効です。
✅ 複数チャネルで情報発信する
- YouTubeやInstagramでコンテンツを展開
- 同じテーマを「動画」「ブログ」「SNS」で届ける
✅ E-E-A-Tをベースにしたコンテンツ強化
- 実名やプロフィールを明記
- 写真・動画・経験談を盛り込む
✅ 検索以外の流入も意識
- SNS経由、LINE公式、YouTube概要欄など、検索に依存しない導線を確保
小まとめ:SEOは「変化」に対応できるかどうか
検索エンジンは「進化」し、ユーザーは「行動」を変えています。
SEOが「終わった」のではなく、**「今までのやり方では通用しなくなった」**というのが、正確な捉え方でしょう。
次章では、**中小企業や士業・店舗経営者などにとっての「SEOの今と未来」**について、具体的な視点で解説します。
中小企業・個人事業主にとってのSEOの今と未来
「SEOは終わった」と言われる中で、特に影響を受けやすいのが中小企業経営者や個人事業主です。
人手や予算の制約がある中、SEO対策に時間やコストをかける意味があるのか?
本章では、中小規模の事業者が抱える悩みを紐解きながら、「今でも効果があるSEO」と「これからのSEOのあり方」について掘り下げていきます。
まだまだ現役:検索流入からの問い合わせは健在
まず知っておいていただきたいのは、Google検索は依然として「問い合わせ」「予約」「資料請求」などの主要な導線であるという事実です。
特に以下のようなケースでは、SEOが大きな成果を生んでいます:
- 地域密着型の整体院が「地域名+整体」で検索1位になり、月間10件以上の新規予約を獲得
- 税理士が「起業 サポート+地域名」で上位表示し、法人からの問い合わせが安定的に発生
- リフォーム業者が「雨漏り 修理+地域名」でSEO対策を施し、緊急案件の問い合わせが増加
これらはすべて、ニーズの強いキーワードで検索され、すぐにコンタクトに繋がるという「SEOの王道的な使い方」です。
SEOの役割:集客の“受け皿”としての価値
SNSや動画での発信が増える今、SEOはそれらと“対立”するものではなく、連携・補完的な存在としての役割が強まっています。
例えば以下のような連携です:
| 施策 | 機能 | SEOとの関係 |
|---|---|---|
| Instagramでサロンの雰囲気を発信 | 認知・ブランディング | プロフィール欄からWebサイトへ導線 |
| YouTubeで税金に関する解説動画を投稿 | 信頼構築・教育 | 動画説明欄にサイトリンク |
| LINE公式で割引クーポンを配信 | リピート・育成 | サイト内に登録フォーム設置 |
つまりSEOは、“検索流入”という導線だけでなく、他チャネルの「着地点」としても機能するのです。
よくある誤解:SEOはお金がかかる、高度な技術が必要?
中小企業の経営者からよく聞く声に、次のようなものがあります:
- 「SEOって専門業者に頼まないと無理でしょ?」
- 「毎月10万円とかかかるんじゃないの?」
- 「自分でブログとか書けないし…」
実際は、最低限の知識と方向性さえあれば、自社で十分対応可能です。たとえば:
- 地域名+業種名のキーワードを自然にサイト内に含める
- お客様の声や実績を丁寧に記事化する
- 営業時間やメニュー、地図を正確にGoogleマップに記載する(MEO)
といった、**「地道だけど効果が出る」**施策は、むしろ大手企業より中小規模の方が強みを発揮しやすいのです。
今後求められるSEOとは?
これからのSEOにおいて大切なのは、**「自分たちの強みや実績を、ネット上にきちんと反映させること」**です。
✅ 具体的には:
- 体験談・事例・導入ストーリーを記事にする
- 専門家としての視点や注意点を交える
- 写真・動画・レビューなどの証拠を添える
- プロフィールや実績を明記する
これはすべて、Googleが評価するE-E-A-Tの要素でもあり、差別化にもつながります。
将来性:SEOは“死なない”が、“変わり続ける”
SEOは「死ぬ」のではなく、「変化する」のです。
とくに今後の動向としては以下が予測されます:
| 項目 | 変化の方向性 |
|---|---|
| 検索順位 | サイトの“内容”より“信頼性”が重視される |
| キーワード選定 | テキストマッチよりも“文脈”重視へ |
| コンテンツ形式 | テキスト+動画+体験談のハイブリッド化 |
| ペルソナ対応 | 決まった層に特化した深掘りが重要に |
小まとめ:中小企業こそSEOの“本質”を理解すべき
SEOは「派手さ」はありませんが、検索される=行動する直前のユーザーに接点を持てるという強力な武器です。
そして何より、一度上位表示すれば安定して集客できる資産になるという点で、広告やSNSとは異なる強みを持ちます。
次章では、そのSEOをどうやって今から実践していくか、**「今すぐできるSEO対策」**にフォーカスして解説していきます。
それでもSEOは有効!今からでもできる対策法
「SEOはオワコン」という声がある一方で、今でも確実に成果を出している事業者がいるのも事実です。
では、彼らは何をしているのか? 特別なツールや予算がなくても、できることはたくさんあります。
この章では、「今からでもできる」「誰でも実践できる」SEO対策に絞ってご紹介します。
コンテンツSEOの再評価:記事を書くことの力
まず、SEOの王道といえば「コンテンツSEO」です。つまり、ユーザーにとって価値ある情報を提供する記事を書くこと。
✅ 中小企業や店舗が書くべき記事例:
- 「初めての方へ」:サービスの流れや安心ポイントを解説
- 「お客様の声」:実際の成功事例や体験談
- 「○○とは?」:自社の専門分野に関する解説記事
- 「よくある質問」:問い合わせ前に解消したい悩みを整理
ここで大事なのは、“自社の強み”や“経験”をきちんと伝えることです。AIでは真似できない「人の経験値」が、評価される時代です。
見落とされがちなE-E-A-T対策
SEOを“やっているつもり”になってしまいがちなのが、この「E-E-A-T対策」。
前章で触れたように、Googleは今「誰が言っているか」「なぜ信頼できるのか」を重視しています。
✅ すぐできるE-E-A-T対策:
| 要素 | 対策例 |
|---|---|
| 経験(Experience) | スタッフ紹介・自社での取り組み事例を記事化 |
| 専門性(Expertise) | 有資格者のコメントや独自の視点を入れる |
| 権威性(Authoritativeness) | 外部メディアや専門団体との関係性を明記 |
| 信頼性(Trustworthiness) | プライバシーポリシー、会社概要、SSLなどの整備 |
つまり、会社案内ページやブログも立派なSEO対策の一部なのです。
ローカルSEO・MEO(マップ対策)の強化
特に実店舗を持つビジネスでは、Googleマップ上での表示=来店のきっかけになります。
これを最適化するのが「MEO(Map Engine Optimization)」です。
✅ やるべきMEO対策:
- Googleビジネスプロフィールの情報を最新に保つ(営業時間/写真/サービス内容)
- 定期的に「投稿機能」で情報発信する
- 口コミへの返信を丁寧に行う
- 店内写真・外観・スタッフ紹介を複数アップする
特にスマホユーザーは、地図アプリからお店を選ぶ傾向が強いため、検索ではなく“地図で選ばれる”時代に対応することが不可欠です。
構造化データ(スニペット)にも注目
Googleはページの内容をより深く理解するために、「構造化データ」という情報を読み取っています。
例えば、
- FAQ形式のページ
- 商品レビュー
- イベント情報
などに「構造化データ」を追加することで、検索結果の表示がリッチになり、クリック率が向上する可能性があります。
簡単に実装できるツールも増えており、専門知識がなくても対応可能です。
スマホ対応・表示速度・SSL:技術面の基本も忘れずに
SEOはコンテンツだけでなく、「ページの快適さ」も評価対象です。特に以下の技術面の要素は重要です:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モバイルフレンドリー | スマホで崩れない/タップしやすい |
| 表示速度の高速化 | 画像の軽量化・余計なスクリプト削除 |
| HTTPS化(SSL対応) | URLが「https://」で始まっているか |
| アクセシビリティ | ALTタグの設定や色の見やすさ |
これらはすべて、Googleが公式にランキング要因として明示している項目です。
「今すぐできる」チェックリスト
以下のチェック項目にひとつでも当てはまらない場合は、SEO改善の余地ありです:
✅ チェックリスト(抜粋):
- 自社名で検索して上位に出てくるか?
- スマホで見たときに読みやすいか?
- ホームページに「よくある質問」ページはあるか?
- ブログ記事の最終更新日は新しいか?
- Googleマップ上に店舗情報が正確に掲載されているか?
小まとめ:「SEOはオワコン」ではなく「進化中」
SEOは確かに“昔のやり方”では通用しなくなっていますが、今の時代に合わせたやり方で続ければ、まだまだ成果が出せる分野です。
しかも、広告と違って「積み上げ型」なので、やればやるほど資産になります。
次章では、このSEOに大きな影響を与えている**「AIとの関係性」**について詳しく解説します。
SEOとAIの関係性:生成AIの登場でどう変わったか?
ChatGPTをはじめとする生成AIの登場は、SEOの世界に大きな衝撃を与えました。
一部では「もう人間が記事を書く必要はない」「SEOはAIに取って代わられる」といった意見もありますが、果たして本当にそうなのでしょうか?
この章では、生成AIがSEOにもたらした影響と、それをどう活用すればよいかについて、現実的な視点で解説します。
AIによる「検索スタイルの変化」
かつては「知りたいことがあればGoogleで検索する」のが当たり前でしたが、現在では**「AIに直接質問する」**という行動が当たり前になりつつあります。
たとえば:
- 「SEOとは何か?」→ Google検索 → 複数のサイトを読む(従来)
- 「SEOってまだ効果あるの?」→ ChatGPTに直接質問(現在)
このように、ユーザーが「検索結果」ではなく「即答」を求めているというトレンドは、SEOのあり方に大きな再定義を迫っています。
AIはSEOを脅かす存在か?
結論から言えば、「AIはSEOを終わらせる存在ではないが、SEOの手法を変化させる存在である」と言えます。
✅ 脅威となる側面:
- AIによって検索回数そのものが減少
- 回答がAIで“完結”してしまい、Webサイトが読まれにくくなる
- 誰でもコンテンツを量産できることで情報の希少性が低下
✅ 可能性を広げる側面:
- AIを活用すればSEOに必要な作業が効率化
- キーワード抽出、構成案作成、リライトが高速に
- 繰り返しの多い業務(例:FAQページの初稿作成)が短時間で可能に
つまり、「敵か味方か」ではなく、“AIをどう使いこなすか”が今後のSEOに問われているテーマなのです。
AIを活用したSEO実践の例
ここでは、実際に使えるAIツールと活用例を紹介します。
| ツール名 | 活用方法 | 具体的なメリット |
|---|---|---|
| ChatGPT | 記事の構成案作成・FAQ生成 | 時間短縮・初心者でも品質の高い案を得られる |
| Google Gemini | ページタイトルやディスクリプションの生成 | クリック率の高い見出しを瞬時に複数提案 |
| Canva(AI連携) | SEO記事用の図解やアイキャッチ生成 | 視覚要素の強化による滞在時間UP |
| Surfer SEO | 競合分析とキーワード密度の最適化 | 上位表示しやすい記事構成を自動で提案 |
これらを**「補助ツール」として使いながら、人間の視点と体験を掛け合わせることで、より強力なコンテンツを作成できます。**
AIライティングとE-E-A-Tの両立は可能か?
よくある疑問として、「AIで書いた記事でもGoogleに評価されるのか?」というものがあります。
Googleの公式見解では、
“AIによるコンテンツであっても、高品質かつユーザーに役立つものであれば評価対象とする”
と明言されています。つまり、「AIだからダメ」ではなく、「読者の役に立つかどうか」が評価基準です。
そのため、以下の工夫が有効です:
- AIでベース記事を生成→人間が体験・エピソードを加える
- 実名・会社名・経歴などを記事に明記する
- 自社サイトやYouTubeと連携し“証拠”を見せる
このように、AIと人間の強みをうまく組み合わせた記事が、今後のSEOでは主流になるでしょう。
生成AI時代のSEOにおける“人間らしさ”の価値
AIが台頭するほど、逆に「人間だからこそ書ける内容」に価値が生まれます。
特に以下のような要素は、AIには難しい領域です:
- 一次情報(取材、現場体験、顧客の声)
- 文脈の深さ(業界特有の空気感、歴史背景)
- 感情・葛藤・判断の記録(なぜそれを選んだか)
SEO対策にAIを活用することは今後の常識となるでしょうが、最終的な勝負は「人としてのリアリティ」であるという事実は、変わらないのです。
小まとめ:AIは“SEO終了”ではなく、“進化の起爆剤”
SEOとAIは敵ではなく、相互補完のパートナーです。
生成AIによって「検索のあり方」「記事の作り方」が変化した今、
我々がすべきことは、新しいツールを“自分の武器”として使いこなすことです。
次章では、SEO以外に注目すべき集客手段として、SNS・動画・広告との連携方法にフォーカスして解説していきます。
SEO以外の集客戦略:SNS・動画・広告の活用
SEOが「オワコン」と言われる背景には、「検索以外にも集客手段が増えてきた」という理由があります。
特に近年は、SNS・動画・Web広告といった多様な集客チャネルが中小企業でも活用可能になってきました。
この章では、SEO以外の集客チャネルの特徴と、SEOとどう組み合わせて活用すべきかについて具体的に解説します。
SNSの役割:共感・拡散・信頼の獲得
SNS(Instagram/X/TikTokなど)は、SEOと比べて「拡散力」と「共感力」に優れています。
特に以下のようなジャンルでは、SNSが圧倒的な効果を発揮します:
| 業種 | 投稿内容の例 | 効果 |
|---|---|---|
| 飲食店 | 今日のランチ写真・お客様の声 | 来店・予約 |
| 美容院 | ビフォーアフター・施術動画 | 信頼獲得・指名 |
| 士業 | 知って得する豆知識・Q&A | 認知・信頼構築 |
ポイントは、SNSは「検索されない情報」を自ら届けるツールということ。
SEOが“待ちのメディア”だとすれば、SNSは“攻めのメディア”です。
YouTube・ショート動画:ビジュアルで伝わる時代
中小企業や個人事業主にとっても、「動画」は今や無視できない集客手段になりました。
特にYouTube・Instagramリール・TikTokといった短尺動画の活用は、以下の理由から非常に効果的です。
✅ なぜ動画が強いのか?
- 一度見れば“信頼”が一気に高まる(顔・声・雰囲気が伝わる)
- アルゴリズムによって“偶然の出会い”が生まれる
- SEO的にも「動画が埋め込まれたページ」は評価されやすい
✅ 具体例:
- 司法書士が「相続登記って必要なの?」を1分で解説
- エステサロンが「初回来店の流れ」をショートで紹介
- 工務店が「リフォーム前後のビフォーアフター」を動画にまとめる
こうした動画は、SEO記事に埋め込むことで滞在時間も向上し、相乗効果を発揮します。
Web広告:即効性のある“エンジン”
SEOが“中長期の集客手段”だとすれば、Web広告は短期で効果が出やすい即効型のツールです。
Google広告(リスティング)、Meta広告(Facebook・Instagram)、YouTube広告などは、予算に応じて柔軟に展開可能です。
広告活用のポイント:
- キャンペーンや新サービスを知ってもらう
- SEOが育つまでの“つなぎ”として活用
- 問い合わせや予約を短期で獲得したいときに有効
ただし、広告費が尽きると集客も止まるため、SEOやSNSと組み合わせて“持続性のある仕組み”にしていくことが重要です。
SEO × SNS × 動画 × 広告の“連携戦略”
集客は「どれか1つ」に頼る時代から、「複数を組み合わせて相乗効果を生む時代」へと進化しています。
そのためには、チャネルごとの役割を理解したうえで、連携させることがカギです。
| チャネル | 目的 | 補完関係 |
|---|---|---|
| SEO | 検索からの安定流入 | 受け皿としての信頼性構築 |
| SNS | 認知・拡散・関係構築 | 情報の即時発信と親近感の醸成 |
| 動画 | 視覚的理解・信頼獲得 | 顧客との距離感を縮める |
| 広告 | 即時の流入・予約獲得 | 補助的エンジンとして機能 |
✅ 例:
YouTube動画で信頼構築 → 概要欄からサイトへ → SEO記事で詳しく理解 → お問い合わせ
小まとめ:今は“ハイブリッド集客”が基本戦略
「SEOだけ」「SNSだけ」ではなく、複数のチャネルをかけあわせてこそ、今の時代に最適な集客ができるようになっています。
SEOは決してオワコンではなく、「他の手段と組み合わせることでより強力になる存在」だということを忘れないでください。
次章では、これまでのまとめとして、中小企業が取るべき2025年以降のSEO戦略の方向性について整理していきます。
2025年以降のSEO戦略まとめと実践ポイント
「SEOはオワコンだ」と言われる背景には、急激な検索環境の変化やAIの台頭があります。
しかし本質的には、“旧来のSEO”が通用しなくなっただけで、“新しいSEO”はむしろこれからのビジネスの基盤になり得るのです。
この章では、これまでの内容を踏まえたうえで、2025年以降において中小企業や個人事業主が意識すべきSEOの方向性と、実践ポイントを整理していきます。
これからのSEOに求められる3つの視点
1. 「検索される場所」が変わった
Google検索だけではなく、YouTubeやInstagram、Googleマップ、そしてChatGPTなどのAIチャットも「検索の場」となっています。
✅ 対応:各チャネルに対応した最適化(動画SEO、MEO、SNS導線など)
2. 「信頼される情報」の定義が変わった
Googleは単なる情報よりも、「誰が、どんな立場で、どんな経験をもとに語っているか?」を重要視しています。
✅ 対応:E-E-A-Tに沿った情報発信(プロフィール、事例、証拠の提示)
3. 「コンテンツ制作の手段」が変わった
ChatGPTやGeminiなどの生成AIにより、構成案・リライト・FAQ作成などの作業が格段に効率化されました。
✅ 対応:AIを補助ツールとして活用し、人間の体験や感情で差別化
中小企業・個人事業主がやるべきSEO戦略【実践チェックリスト】
以下は、2025年以降において「本当に成果につながるSEO施策」を一覧化したチェックリストです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ✅ Webサイトの目的が明確か? | 問い合わせ、予約、来店など「行動」に直結しているか |
| ✅ MEO対策ができているか? | Googleビジネスプロフィールは最新か/口コミ返信しているか |
| ✅ ブログやコラムは定期更新しているか? | 専門性や実体験をベースにした記事が書かれているか |
| ✅ E-E-A-T要素を意識しているか? | 会社情報、執筆者情報、事例・レビューなどが掲載されているか |
| ✅ 動画やSNSとの連携があるか? | 動画埋め込みやInstagram導線などが設置されているか |
| ✅ AIを活用して時短しているか? | ChatGPTなどを使って構成・草案・要約を効率化しているか |
今こそ「SEO×〇〇」でシナジーを生む時代
SEOは、単体で完結するものではなくなっています。
2025年以降は特に以下のような組み合わせが効果的です:
- SEO × YouTube → 滞在時間・信頼度アップ(動画埋め込み)
- SEO × SNS → 拡散・話題化→検索流入へ
- SEO × AI → 作業効率化と情報の網羅性アップ
このように、「SEOは集客の入り口」ではなく、“検索されるブランド”になるための設計図として再定義されつつあるのです。
SEOに“未来がある人”の共通点
成果を出し続けている企業には、以下の共通点があります:
- デジタルに苦手意識はあっても、チャレンジする意思がある
- 検索だけに依存せず、情報を発信し続けている
- 「正しいことを、わかりやすく、丁寧に伝える」姿勢がある
これは、大企業だけでなく、個人事業主や地域密着型の中小企業こそ活かせる強みです。
小まとめ:SEOは“進化する資産”
「SEOは終わった」と嘆く前に、自社の発信の仕方を見直してみましょう。
検索されることは、今なお“信頼の入り口”であり、検索で上位に出ることは“専門家として認められる”ことでもあります。
2025年以降、SEOは単なるテクニックではなく、
**“企業の信頼と価値を築くための資産形成”**として、進化を続けていくのです。
よくある質問(FAQ)
SEOは本当にもう効果がないのでしょうか?
いいえ、SEOは今も効果があります。ただし「昔のようにキーワードを詰め込めば上がる」時代ではありません。現在は、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視したコンテンツや、ユーザーの検索意図を満たす情報設計が求められています。
中小企業でもSEO対策はできますか?
はい、可能です。むしろ地域性や専門性を活かせる中小企業のほうが、上位表示されやすい傾向があります。ブログ、Googleマップ(MEO)、FAQページなど、実践できる施策も多く、予算をかけなくても成果が出せます。
SEOとSNSはどちらを優先すべきですか?
目的によります。短期的な認知拡大や話題化を狙うならSNS、長期的に問い合わせや予約を増やしたいならSEOがおすすめです。最も効果的なのは、「SNSで拡散→SEO記事で信頼構築」という連携です。
AIで書いた記事でもSEO対策になりますか?
はい。ただし、AIが生成しただけの情報では評価されにくいため、人間の体験や見解を加えることが重要です。AIを「効率化ツール」として活用しつつ、E-E-A-Tを満たす形で最終調整することがSEO成功の鍵です。
SEO対策の成果が出るまでにどれくらいかかりますか?
通常、3〜6ヶ月程度で成果が見え始めると言われています。ただし、ローカルSEO(MEO)やFAQページなどは、より短期間で効果が出ることもあります。継続的な更新と改善が重要です。
参考外部記事
1. Google 検索セントラル(旧ウェブマスター向け公式ヘルプ)
Google公式のSEO方針や評価基準を確認できるページ。E-E-A-Tや構造化データなどのガイドラインも網羅。
2. Search Engine Journal - 最新のSEOニュースと分析
SEO業界の最新トレンドやアルゴリズム変化を継続的にチェックできる専門メディア。
3. Yoast SEO Blog
WordPressユーザーにも馴染み深いYoastによる、実践的なSEO対策解説。初級〜上級者向け。
4. Neil Patel Blohttps://neilpatel.com/g(ニール・パテル)
SEO・コンテンツマーケティング・AI活用など、実践的なアドバイスが豊富な世界的マーケターのブログ。
5. Moz Blog
SEOの本質やツールの活用法、最新トレンドを網羅。信頼性の高いデータに基づいた分析記事が多数。
参考関連記事
生成AIでビジネス革命!中小企業・個人事業主の成功事例と活用法 | AIビジネス最前線
デジタルマーケティングの世界は日々進化していますが、ついていくのが大変だと感じていませんか? 特に中小企業や個人事業主の皆さまにとって、新しい技術を取り入れるのは難しく感じるかもしれません。 でも、ご安心ください。 この […]
AIでコンテンツ最適化の全て:初心者でもわかる効果的なSEO戦略
現代のデジタルマーケティングにおいて、「AI コンテンツ最適化」は重要なキーワードとなっています。AIを活用することで、少ないリソースでも大きな成果を上げることが可能です。 しかし、専門用語が多くて分かりづらい、何から始 […]
生成AI(Generative AI)のビジネス活用と成功事例:中小・個人事業主向け完全ガイド
生成AI(Generative AI)は、ビジネスに革新をもたらす技術で、テキスト、画像、音声、動画などの新しいコンテンツを自動的に生成します。スモールビジネスオーナーとして、この技術をどのように活用できるのかを具体的な […]
投稿者プロフィール

- 動画・映像マーケター・WEB集客・AI集客サポート
-
映像 × 生成AI × デジタルマーケティング
“伝える”だけでなく、“成果を生み出す”戦略的な映像マーケティングを。
13年以上にわたり、デジタルマーケティングコンサルタントとして
企業・店舗・士業・医療・観光など多様な業界の集客を支援。
外資系製薬会社、不動産・リフォーム会社、コンサルティング企業、
リスクマネジメント分野などで
広告運用・Googleアナリティクス解析・SEO/MEO対策を通じ、
継続的な集客導線とブランド成長に貢献してきました。
現在は、映像と生成AIを融合したマーケティング支援に注力。
YouTubeチャンネル運用、PR・採用・リクルート動画、動画広告、対談・インタビュー動画など、
戦略設計から撮影・編集・運用まで一貫してサポートしています。
撮影においては、被写体の魅力を最大限に引き出すために
カメラワーク・照明・音声のディレクションから、
必要に応じてドローン撮影なども組み合わせ、
表現力の高い映像を実現します。
また、生成AIを活用した台本制作・構成設計・SNS投稿文作成・分析自動化など、
AIによる効率化と創造性の両立を実現。
**「AI × 映像 × 集客設計」**の掛け合わせで、
これまでにない成果型の映像マーケティングを提供しています。
これまでに登録者150万人超のYouTubeビジネスチャンネル立ち上げに参画。
戦略構築・演出ディレクション・改善分析を担当し、
視聴維持率・エンゲージメント向上に貢献しました。
Yahoo!広告認定資格を保有し、10年以上の広告運用経験から、
**流行に左右されない「持続的な集客導線」**を設計します。
今の時代、動画は「映える」ためではなく、「動かす」ために使うもの。
データ・AI・映像表現を融合し、
企業の想いを“伝わるストーリー”として形にするパートナーであり続けます。
最新の投稿
 AI2025年11月29日AI時代に必須のスキル!成果を出すプロンプトの書き方【初心者向け基礎講座】
AI2025年11月29日AI時代に必須のスキル!成果を出すプロンプトの書き方【初心者向け基礎講座】 AI2025年11月11日【AI時代の集客術】GEOとSEOの違いとは?中小企業が今すぐすべき対策を徹底解説
AI2025年11月11日【AI時代の集客術】GEOとSEOの違いとは?中小企業が今すぐすべき対策を徹底解説 AI2025年11月1日YouTubeサムネイルイラスト用プロンプト完全ガイド
AI2025年11月1日YouTubeサムネイルイラスト用プロンプト完全ガイド AI2025年10月30日世界で使われるYouTube台本フォーミュラ10選
AI2025年10月30日世界で使われるYouTube台本フォーミュラ10選
LINEからのお問合せ
LINEからご予約の場合、下記内容をお書き添えくださいませ。
動画(撮影・編集・YouTube)に関すること
マーケティングやAIプロンプト設計 に関するご相談も承っております。
「オリジナルのChatGPTプロンプトを作りたい」「AI活用をビジネスに取り入れたい」なども、お気軽にご相談ください。
- あなたの現在の状態をできるだけ詳しくお聞かせください
- あなたのご要望を教えてください
- オンライン相談ご希望の有無
このほか マーケティング に関するあらゆるご相談も承っております。
\ 私が担当いたします /
代表 松井 要
14年以上のデジタルマーケティング経験を持ち、これまで多数の業界で成果を上げてきました。
350万人超の登録者を誇るYouTubeビジネスチャンネルの立ち上げにも参画し、戦略設計から運用まで幅広く支援。広告運用やSEO・MEO対策を通じて、多くのクライアントの集客課題を解決してきました。
現在は、映像制作やドローン空撮を活用したPR・集客支援にも注力。特に、インタビュー動画や施設紹介映像など「伝わるストーリー設計」によるブランディング支援を得意としています。
さらに、AIを活用したデータドリブンなマーケティング施策にも対応。業界や流行に左右されない、持続可能で成果の出る集客戦略をご提案します。
問い合わせフォームがいい人はこちらから