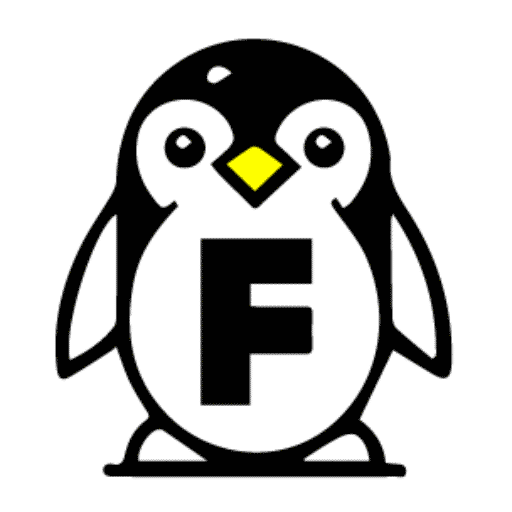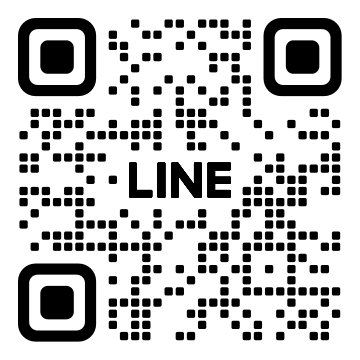なぜ「SEO対策は意味がない」と言われるのか?

「SEOはもう意味がない」「効果が出ない」「やっても無駄」——このような声を聞いたことがある方は少なくないでしょう。特に中小企業や個人事業主の間では、時間とコストをかけた割に成果が見えにくいSEO施策に疑問を感じる人が増えています。では、なぜこうした「意味ない」とされる声が広まっているのでしょうか?その背景には、いくつかの明確な理由があります。
1. 結果が出るまで時間がかかる
SEOは即効性がないマーケティング手法です。たとえば、ブログ記事を公開してから検索順位が安定するまでに、早くても3〜6ヶ月、長ければ1年以上かかることもあります。短期的な売上や予約獲得を求める事業者にとって、「待ち」の戦略であるSEOは不向きに感じられるのも無理はありません。
2. Googleのアルゴリズムが頻繁に変化する
Googleは年に数百回ものアルゴリズム更新を行っており、**「昨日まで1位だったページが突然圏外に飛ばされた」**という事例も珍しくありません。この不安定さが、SEO対策に対する不信感を招いています。
3. 業者任せで成果が不明瞭になる
「SEO業者に依頼したけど、何をやっているかよく分からない」「レポートだけ届くけど、問い合わせは増えていない」——これは典型的な“ブラックボックス型SEO”の問題です。施策の中身と成果が結びつかないことで、「本当に意味があるのか?」と疑念が生まれやすくなります。
4. SNSや動画の影響力の拡大
2020年代に入り、検索よりもSNSやYouTubeで情報を探す人が増加しました。特に20代〜30代の若年層は、InstagramやTikTok、YouTubeを活用して店舗やサービスを探す傾向にあります。この行動変化により、「SEO=検索対策」に固執しても効果が出にくくなっている側面があります。
5. ChatGPTなどAIの台頭による検索習慣の変化
ChatGPTやGeminiのような生成AIの普及により、ユーザーが「調べ方」そのものを変えてきている点も見逃せません。単なるキーワード検索ではなく、AIに直接相談する形で情報を得る時代が近づいています。こうした背景も、「SEO不要論」に拍車をかけているのです。
6. コンテンツ過多によるレッドオーシャン化
Google検索結果には**「似たようなコンテンツ」が大量に存在**します。「SEOに強い記事」を量産しても埋もれてしまい、読まれないことも珍しくありません。この競争過多状態に対して、効果を感じにくくなるのは当然です。
✅ ポイントまとめ
- SEOは時間がかかり、短期的成果を求めるビジネスには不向き
- Googleの変動や外注依存で「効果が見えない」リスクがある
- SNSや生成AIにユーザーが流れている現実がある
- 競合が多すぎて「やる意味がない」と錯覚しやすい
SEOが通用しないと言われる4つの業種とその理由

「SEOは業種によっては意味がない」と言われることがあります。実際に、SEOの費用対効果が合わずに撤退する企業も少なくありません。ここでは、SEOが特に通用しにくいと言われる4つの業種を取り上げ、なぜ効果が出にくいのかを分析します。
1. 飲食店(特に地方や個人経営)
飲食業界では「即日予約」「近隣で検索」のように、タイムリーでローカルな検索行動が主流です。SEOで上位表示されたとしても、Googleマップや口コミアプリ(例:食べログ、Retty、Googleビジネスプロフィール)で完結するユーザーが多く、Webサイトまで見られないことが多いのです。
❌ SEOが効きにくい理由:
- ユーザーはWebサイトではなくGoogleマップ上で選ぶ
- 「駅名+ランチ」などのキーワードで競合多数
- MEO(ローカルSEO)の方が効果的
2. 医療・歯科・整体などの治療系サービス
この分野はGoogleの「YMYL(Your Money or Your Life)」カテゴリに属し、検索順位に影響を与える評価基準(E-E-A-T)が非常に厳しい業界です。信頼性や公的機関の情報が優先され、個人院のページはなかなか上位に上がらないことも。
❌ SEOが効きにくい理由:
- YMYLに該当し、Googleが慎重に判断する領域
- 医療広告ガイドラインで表現の制限が多い
- 上位表示できても問合せにはつながらない場合も
3. 一次産業(農業・漁業など)
生産者が自ら販売をするケースが増えていますが、検索からの導線構築が難しいことが課題です。商品名や生産者名で検索されにくく、「〇〇農園 じゃがいも」などのニッチワードでは流入が限られます。
❌ SEOが効きにくい理由:
- そもそも検索される機会が少ない
- 商品の単価に対してSEOコストが見合わない
- ECサイトの集客にはSNSの方が有利なことも多い
4. ニッチなBtoBビジネス
法人向け商材や専門機器などのBtoB領域では、そもそも検索ボリュームが小さいケースが多く、SEOで上位を取っても流入数がごくわずかということがあります。また、業界的に紹介や展示会ベースでの営業が強いこともあり、SEOが主な営業手段になりにくいのです。
❌ SEOが効きにくい理由:
- ターゲットが狭く、検索ボリュームが小さい
- Web経由での商談化が難しい
- 業界のキーパーソンは検索ではなく人脈で動く傾向
✅ 業種によって向き・不向きはある
SEOはすべての業種にとって万能ではありません。
以下のように整理するとわかりやすいです。
| 業種 | SEO適性 | 補足戦略 |
|---|---|---|
| 飲食 | △ | MEO/SNS活用が優先 |
| 医療 | △ | E-E-A-T強化+ローカル戦略 |
| 農業 | △ | SNSとEC連携が効果的 |
| BtoB | △ | コンテンツマーケ+展示会やセミナーと併用 |
🔍 重要な視点
「SEOは意味がない」ではなく、「自社にとってはコスパが合わないだけ」というケースがほとんどです。マーケティング施策は業種特性と相性を見極めて判断することが重要です。
SEO対策が効果を出さない3つの典型パターン

SEO対策を実施しても、「検索順位が上がらない」「問い合わせが来ない」「何が悪いか分からない」といった悩みを持つ経営者は少なくありません。こうした声の多くは、実は**“やり方の問題”**に起因しています。ここでは、効果が出ないSEOの典型的な3つのパターンを紹介します。
1. 業者任せで「丸投げ型」の失敗
SEOを専門業者に依頼した結果、毎月レポートは届くが成果に結びつかないというケースは非常に多いです。これは、施策の内容がブラックボックス化し、何のためにどんな改善をしているのかが見えないことが原因です。
❌ よくある状況:
- キーワードの提案が「検索ボリューム順」でしかない
- コンテンツの中身に専門性がなくテンプレート化している
- HTMLの微調整に終始し、ビジネス成果に直結しない
✅ 解決策:
- 施策内容を毎月「わかりやすい言葉」で説明してもらう
- 経営者も最低限のSEO知識を持つ(用語理解など)
- 「問い合わせ数」「CV率」など成果軸での評価を導入する
2. 時代遅れのSEO施策を続けている
かつて効果があった方法(キーワード詰め込み、被リンク大量取得など)を今でも続けているケースでは、Googleからの評価が下がり、逆効果になることすらあります。
❌ 古いSEO施策の例:
| 手法 | 現状 |
|---|---|
| キーワードを大量に詰め込む | スパム扱いで逆効果 |
| 無理に長文にする | ユーザー離脱率が上がる |
| 外部リンク購入 | ペナルティ対象 |
✅ 今のSEOに必要な視点:
- 「ユーザーの検索意図」に応えた自然な文章構成
- 見やすさ・読みやすさを重視したレイアウト設計
- 自然な被リンクやサイテーション(引用)を獲得するための専門性ある情報発信
3. 全体戦略がない「コンテンツ量産型」
「とにかく記事を出せばいい」「週に1本ブログを書いていれば大丈夫」といった量頼みの戦術では、もはや効果は出ません。検索上位になるには、戦略的にサイト構造やコンテンツの役割分担を設計しなければなりません。
❌ よくある失敗例:
- 「記事一覧」に同じような内容のブログがずらり
- キーワードカニバリ(同じワードで複数記事が競合)
- CTAが弱く、せっかくのアクセスがコンバージョンにつながらない
✅ 成果を出すコンテンツ設計の考え方:
- トップページ → サービス案内 → 専門記事 → 問い合わせ という導線を明確に
- キーワードマップを作成し、記事の目的と階層を設計
- 読者の行動を促すCTAを必ず配置する
✅ 成果が出ない原因は「やらないこと」より「やり方」にある
「SEOは意味がない」と決めつける前に、一度立ち止まって**“戦略そのものが適切かどうか”**を振り返る必要があります。特に、次の3点に注意して再設計すると、成果の兆しが見えてくることがあります。
🔍 チェックリスト
- SEO業者の内容を理解し、自社の目的と照らしているか?
- 古い手法に頼っていないか?(被リンク・長文偏重など)
- 全体の導線が整っているか?(TOP→LP→CVの流れ)
それでもSEOが「意味ある」理由とは?
「SEOは意味がない」と感じる人がいる一方で、しっかりと成果を出している企業や個人も存在します。実際に、SEOはうまく設計すれば「低コストで持続的な集客チャネル」として非常に強力です。ここでは、SEOがいまだに“意味ある施策”である理由を掘り下げていきます。
1. 信頼構築とブランド認知につながる
検索上位に表示されることは、ユーザーにとって「この会社は信頼できるかも」と感じさせる心理的ブランディング効果があります。検索経由でたどり着いたユーザーは、SNSよりも信頼性重視で情報を探している層が多いため、コンバージョンにもつながりやすいのです。
✅ たとえば:
- 「〇〇市 整体院」で上位表示されている → 地元で人気があると認識されやすい
- 「〇〇+悩み解決方法」で自社ブログがヒット → 専門性のある企業として認知される
2. 長期資産としての「記事・コンテンツ」
SEOで作ったページは、広告と違って出稿を止めても表示され続けるのが最大の魅力です。一度、検索1位を獲得した記事は、数ヶ月〜数年にわたって持続的にアクセスを生む資産になります。
✅ コンテンツ資産の一例:
| 記事タイトル | 公開日 | 月間流入数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 「社労士 SEO対策の基本」 | 2022年3月 | 約700PV | 安定して集客中 |
| 「整体院 ブログ ネタ集」 | 2023年9月 | 約550PV | リライトで順位上昇中 |
3. 広告に依存しない安定集客
SEOで流入した顧客は、広告クリックと違い“興味関心ベース”で訪れているため質が高いのが特徴です。また、広告費を毎月かけ続けることに不安がある事業者にとって、SEOは広告依存からの脱却手段にもなります。
✅ 費用比較(例):
| 集客手段 | 初期費用 | 維持費用 | 成果の継続性 |
|---|---|---|---|
| リスティング広告 | 月5〜30万円 | 毎月課金 | 費用を止めた瞬間ゼロに戻る |
| SEO記事(1本) | 2〜5万円 | リライトや分析コストのみ | 長期的に集客可能 |
4. 「指名検索」の入口になる
SEOによって認知を得た後に、ユーザーが「会社名+サービス名」で検索するケースは少なくありません。これは指名検索と呼ばれ、顧客の“購買前の最終確認ステップ”として極めて重要です。
例:「Asahi整骨院 ブログ」で指名検索 → ホームページ確認 → 予約ページへ誘導
このように、**「SEO経由→指名検索→成約」**という流れをつくることが、今でもSEOが機能する強力な理由です。
5. 他のチャネルと連携しやすい
SEOは、SNSや動画、メルマガ、広告など他チャネルとの相互強化が可能です。たとえば、YouTube動画を記事に埋め込んだり、ブログ記事をSNSで拡散したりすることで、SEOとSNSのハイブリッド戦略が構築できます。
✅ 「SEO=古い」ではなく「設計次第で今でも強い」
「SEOは意味があるか?」という問いに対しての答えは、**“設計次第で意味は十分にある”**です。特に、長期的に信頼性やブランド力を高めたい業種にとっては、地道でも確実に効いてくる武器なのです。
2025年以降のSEOはどう変わる?AI時代の新常識
「SEOはオワコン」という言葉がささやかれる背景には、検索エンジンの進化とユーザー行動の変化があります。特に2024年から急激に進んだ生成AIの普及や、Google検索のSGE(Search Generative Experience)導入は、SEOの未来を大きく左右するトピックです。この章では、2025年以降のSEOがどう変化するのかをわかりやすく解説します。
1. SGE(生成AI検索)の影響
SGEとは、Googleが進めているAIによる検索補助機能で、検索結果の上部にAIが要約した回答が表示されるというものです。この結果、従来の検索順位1位よりも、SGE内で取り上げられることの方が重要になってきます。
✅ ユーザーの変化:
- 従来:「検索→サイトクリック→情報収集」
- これから:「検索→SGEのAI要約で完結」
📉 リスク:
- 自社ページが検索1位でも、SGEの要約に含まれなければクリックされない
- 逆に、上位でなくてもSGEに引用されれば流入が得られる
2. SEOは「AIに引用される設計」が必須に
AIは、「誰が・なぜ・どんな文脈で」発信しているかを重視するため、**E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)**がより一層重要になります。これはGoogleのアルゴリズムだけでなく、AIによる要約の根拠としても評価基準になるからです。
✅ AI時代に強いコンテンツの特徴:
- 体験談や事例ベースで具体的に書かれている
- 医療や法律などのYMYL領域では、専門家の記述が明記されている
- 記事内に信頼性の高い外部リンクが引用されている
3. 「動画や音声コンテンツ」の影響力が拡大
GoogleやBingは、動画やポッドキャストの文字起こしデータもインデックス対象としています。つまり、テキストだけでなく動画の中身もSEO評価に組み込まれる時代です。
例:「SEO対策 とは」の検索結果に、YouTube動画の内容を要約した文章が表示されることも増えている。
✅ 対策:
- ブログにYouTube動画を埋め込み、相互にキーワードを最適化
- 動画のタイトル・説明欄・字幕にSEOキーワードを含める
- ポッドキャストの音声をテキスト化して記事化する
4. 「会話型検索」とロングテールの重視
ユーザーはChatGPTのような会話型AIに慣れてきたため、検索クエリも「〇〇って何?」「△△するにはどうすればいい?」と質問形式での検索が増加しています。これは従来の単語検索では拾えなかったロングテールワードが強くなっていることを意味します。
✅ 対応のポイント:
- タイトルや見出しに「質問文」を取り入れる(例:「なぜSEOは意味がないと言われるのか?」)
- Q&A形式の構成(=FAQ)をページに挿入する
- 会話風のやさしいトーンでライティングすることで、AIからも引用されやすくなる
5. SEOは「単独戦術」から「統合戦略」へ
SEOはもはや単独で勝負する時代ではありません。SNS・YouTube・広告・メールマーケティングなどと連携し、複数チャネルで一貫したコンテンツを発信することが信頼性と評価を高めるカギになります。
例:ブログ→SNSでシェア→YouTubeで補足動画→メルマガで送付→AIに引用
✅ まとめ:SEOは終わらない。ただ「進化に適応できない人」は置いていかれる
SEOは今後も進化しながら存続します。大切なのは、「古い手法を続けること」ではなく、AI・音声・動画・ユーザー行動の変化を理解し、柔軟にアップデートしていくことです。特に2025年以降は「検索される」から「引用される」時代へとシフトしているのです。
効果的なSEO施策とは?やるべきこととやめるべきこと
「SEOは意味がない」と感じるのは、多くの場合“間違ったやり方”が原因です。2025年現在でも、正しい施策を実行すればSEOは十分に機能します。この章では、**やるべきこと(Do)と、やめるべきこと(Don't)**を具体的に整理しながら、実践的なSEOの考え方を解説します。
✅ やるべきこと(Do)
1. ユーザー視点に立ったキーワード設計
ただ検索ボリュームがあるだけで選ぶのではなく、**「ユーザーがどんな目的で検索するのか」**を深掘りしてキーワードを選定することが重要です。
例:「SEO 意味ない」→「なぜ意味がないと言われているのか」「効果が出ない原因は?」
✅ ヒント:Googleのサジェスト機能や「People Also Ask」を活用
2. サイト構造と導線の設計
検索でたどり着いた読者が、自然と問い合わせ・資料請求・予約へと流れるように、導線(UX)を明確にすることが成果に直結します。
✅ 例:
- 記事下に「関連するサービスページへのリンク」
- サイドバーに「無料相談バナー」
- トップページ → サービス説明 → 事例記事 → お問い合わせ という構成
3. コンテンツの品質とE-E-A-Tの強化
GoogleとAIに「信頼できる情報源」と認識されるには、**E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)**を意識したライティングが必須です。
| 要素 | 具体策 |
|---|---|
| 経験(Experience) | 自分の体験談・事例を盛り込む |
| 専門性(Expertise) | 資格、経験年数、実績を記載 |
| 権威性(Authoritativeness) | 他メディアや行政サイトからの引用・被リンク |
| 信頼性(Trustworthiness) | 会社情報・代表者名・住所・プライバシーポリシーを明記 |
4. 定期的なリライトとデータ分析
1回書いて終わりではなく、検索順位・クリック率・直帰率などをチェックしながら、定期的な見直しが必要です。
✅ 使用ツール例:
- Google Search Console(検索クエリ、CTR確認)
- Google Analytics(直帰率、滞在時間分析)
- Ahrefs/Ubersuggest(キーワード順位・競合分析)
❌ やめるべきこと(Don't)
1. 無理なキーワード詰め込み
「SEOに強くなるためにキーワードを繰り返す」手法は、かえってスパム判定される原因になります。自然な文脈で、読者が読みやすい形で盛り込むのが基本です。
例(悪い):「SEO SEO SEO SEO対策をするならSEOが大事」
例(良い):「SEO対策を正しく行えば、検索上位に表示されやすくなります」
2. 記事の量産だけを目的にする
「とにかく本数を増やす」ことを優先してしまうと、質が落ち、Googleにも読者にも評価されにくくなります。1記事ごとの完成度(読了率・滞在時間)を高めるほうが重要です。
3. 中身のない「薄いページ」の乱立
文字数だけを増やす目的で、内容の薄いページを量産すると、サイト全体の評価が下がる可能性があります。1ページ=1テーマで、読者の悩みを丁寧に解決する設計が理想です。
4. AIに丸投げしただけの無機質なコンテンツ
AIライティングツールをそのままコピペするだけでは、**どこかで見たような“魂のない記事”**になります。AIの出力をベースに、自社の経験や独自視点を必ず加えることが求められます。
🛠 成果を出すSEOのチェックリスト(実用)
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| キーワード設計 | ユーザー意図に沿った内容になっているか? |
| 導線設計 | 問い合わせや予約への動線が明確か? |
| コンテンツ構成 | E-E-A-Tを意識しているか? |
| モニタリング | 毎月の順位やCV率をチェックしているか? |
SEOが向いていないビジネスの代替戦略とは?
SEOはすべてのビジネスにとって万能な集客手法ではありません。特に「即効性を求めるビジネス」や「検索されにくい商品・サービス」を扱う業種では、SEOだけに依存するのは危険です。では、**SEOが難しい・向いていない場合は、どんな代替戦略を取るべきなのでしょうか?**実際に成果が出ている代替手段を紹介します。
1. SNSマーケティング(Instagram/X/TikTok)
検索される前に、発見される仕組みを作るのがSNSの強みです。特に飲食、美容、雑貨、観光業など「ビジュアル訴求」が重要な業種では、SEOよりもSNSが圧倒的に効果的です。
✅ 向いている業種:
- 飲食店(カフェ・居酒屋など)
- 美容サロン・ネイル・エステ
- 雑貨・アパレル・クラフト販売
- 旅館・観光地
✅ 活用ポイント:
- Instagram → ハッシュタグ検索+ストーリーズで露出
- TikTok → 動画で来店のきっかけを作る
- X(旧Twitter)→ 業界人やファンとの距離感を縮める
2. MEO対策(Googleマップ検索対策)
特に地域密着型ビジネスにおいては、SEOよりもGoogleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)を活用したMEOの方が早く成果が出ます。
✅ 成果例:
- 「〇〇市 美容室」「△△駅 カフェ」などで地図検索するユーザーが増加中
- クチコミ対策や写真投稿を強化すればGoogleマップの上位表示が可能
✅ やるべきこと:
- 定期的に写真・投稿・イベント情報を更新
- 口コミに返信して信頼感をアップ
- 営業時間や定休日を常に最新に保つ
3. リスティング広告(Google広告/Yahoo広告)
「すぐに問い合わせがほしい」「キャンペーンを短期で打ちたい」という場合、SEOよりリスティング広告の方が成果に直結しやすいです。キーワードの入札次第で検索結果の最上部に表示できるため、特に緊急性の高いサービスに効果的です。
✅ 向いている業種:
- 士業(税理士・弁護士など)
- 緊急対応系(鍵開け・水漏れ修理)
- 季節キャンペーン型商品
✅ 注意点:
- キーワード選定により費用対効果が変動
- LP(ランディングページ)の品質が問われる
- 継続には予算確保が必要
4. YouTubeやショート動画での集客
SEOが難しい業種でも、映像コンテンツを活用すれば“指名検索”やSNS流入を増やせる可能性があります。特に中小企業・店舗・専門職で動画を活用している事例が急増しています。
✅ 活用事例:
| 業種 | 活用内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 整体院 | ビフォーアフター動画 | 信頼獲得+指名検索が増加 |
| 税理士 | ショート動画で制度解説 | 認知度アップ→HP流入 |
| 雑貨屋 | 商品紹介ショート | ECサイトへの導線強化 |
5. 紹介・コミュニティマーケティング
SEOを使わずに、既存顧客からの紹介や、業界内コミュニティからの広がりを狙う戦略も有効です。特に士業やBtoB系ビジネスは、「紹介」こそが最も信頼性の高い営業チャネルになります。
✅ 戦術例:
- リファラル制度の導入(紹介者に特典)
- セミナー・勉強会の開催 → 信頼構築&案件化
- LINE公式アカウントでのクローズド配信
✅ 最適な手法は「業種」と「目的」で選ぶべき
| 目的 | 向いている戦略 |
|---|---|
| 即効性がほしい | リスティング広告、SNS広告 |
| 地域で認知されたい | MEO、口コミ強化、地域密着YouTube |
| 指名検索を増やしたい | YouTube、SNS、ブログ×動画連携 |
| コストを抑えたい | コミュニティ形成、紹介制度の構築 |
SEOにこだわりすぎず、「目的に合った戦術を選ぶ」ことで、集客の失敗リスクは大きく減らせます。本当に意味のある施策を選ぶためには、自社の状況とリソースに合ったマーケティング戦略を柔軟に設計することが重要です。
まとめ:SEOは「意味がない」のではなく「やり方次第」
ここまでご紹介してきたように、「SEO対策は意味がない」と言われる背景には、間違った理解や実行の仕方があります。SEOは時代遅れでも無駄でもなく、変化に適応すれば今なお有効な集客手段です。
✅ 要点まとめ(5つ)
- 「意味がない」とされるのは、成果が出にくいパターンに陥っているだけ
業者任せや時代遅れの手法が効果を出せない最大の要因。 - 業種や目的によって、SEOが向いていないケースもある
飲食店、一次産業、緊急系サービスなどは、MEOや広告との組み合わせが重要。 - 正しい設計であれば、SEOは資産になる
長期的な集客チャネルとして、ブランド構築にも効果的。 - 2025年以降のSEOは「AI時代」に最適化すべき
SGEやChatGPTなどの普及により、「検索される」より「引用される」コンテンツが評価される。 - SEOだけに頼らず、動画・SNS・広告と連携して統合戦略を組むことが鍵
単独戦術ではなく、相互補完的な仕組みで効果を最大化できる。
🎯 読者へのアクション(CTA)
あなたのビジネスにとって、「SEOは意味がない」と感じていたなら、
まずはその理由を正しく分析し、何を変えるべきかを見直してみてください。
✔︎ SEOを本格的に改善したい方は、専門家への相談をおすすめします。
✔︎ SNSや動画施策を取り入れたい場合も、組み合わせのコツを学ぶことが重要です。
🔗 関連記事の紹介
FAQ(よくある質問)
Q1. 本当にSEOはやる意味があるのでしょうか?
A. はい、やり方と戦略次第で意味は十分にあります。
特に中長期的な集客や信頼構築、ブランド認知を目的とした場合、SEOは今も強力な手法です。ただし、業種や目標によっては他の手段との組み合わせが効果的なケースもあります。
Q2. SEOをやっても結果が出ないのはなぜですか?
A. 多くの場合、戦略や設計のミスが原因です。
たとえば、ユーザー意図を無視したキーワード選定や、効果が不明な外注、時代遅れの施策を続けていると成果が出ません。定期的な改善とデータ分析が不可欠です。
Q3. MEOやSNSと比べて、SEOをやるメリットは?
A. 信頼性と検索経由の「高意欲ユーザー」を獲得できる点です。
SNSは拡散力がある一方で、関心の浅いユーザーも含まれます。SEOは情報を求めて検索してくるユーザーが多く、購買や問い合わせにつながる確率が高くなります。
Q4. AI時代にSEOはどう変わるの?
A. 検索から“AIによる引用”が重視される時代へ進んでいます。
GoogleのSGEやChatGPTのようなツールは、信頼性・専門性の高い情報を優先的に引用します。E-E-A-Tの強化や、会話調のコンテンツ作成がより重要になります。
Q5. SEOが向いていないと感じたらどうすればいい?
A. SNS、MEO、YouTubeなど、目的に応じた代替手段を活用しましょう。
SEOが難しい業種では、SNSでの認知獲得、Googleマップでのローカル集客、動画での信頼構築などが効果的です。すべてをSEOで解決しようとせず、複数の手段を組み合わせる視点が重要です。
参考外部記事
1. Google 検索の仕組み
Google公式が提供する「検索エンジンがどのように情報を収集し、順位を決定しているか」を解説したページ。SEOの原点を理解したい人に最適。
2. Search Engine Journal - Is SEO Still Worth It in 2025?
「2025年にSEOはまだ意味があるのか?」をテーマに、海外SEOエキスパートが現状と未来を分析。グローバルな視点が得られる貴重な記事。
3. Moz - What is E-E-A-T in SEO?
Googleが重視する「経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)」について詳しく解説。高評価コンテンツを作るためのヒントが得られる。
4. Google Search Central Blog
Google公式の検索チームによる最新アップデート情報。アルゴリズムの変更やSEOに関するガイドラインを追いたい方向け。
5. HubSpot Blog - SEO Strategy in 2025
生成AIや検索行動の変化をふまえた2025年版SEO戦略ガイド。初心者〜中級者にわかりやすく、実践的な内容が満載。
投稿者プロフィール

- 動画・映像マーケター・WEB集客・AI集客サポート
-
映像 × 生成AI × デジタルマーケティング
“伝える”だけでなく、“成果を生み出す”戦略的な映像マーケティングを。
13年以上にわたり、デジタルマーケティングコンサルタントとして
企業・店舗・士業・医療・観光など多様な業界の集客を支援。
外資系製薬会社、不動産・リフォーム会社、コンサルティング企業、
リスクマネジメント分野などで
広告運用・Googleアナリティクス解析・SEO/MEO対策を通じ、
継続的な集客導線とブランド成長に貢献してきました。
現在は、映像と生成AIを融合したマーケティング支援に注力。
YouTubeチャンネル運用、PR・採用・リクルート動画、動画広告、対談・インタビュー動画など、
戦略設計から撮影・編集・運用まで一貫してサポートしています。
撮影においては、被写体の魅力を最大限に引き出すために
カメラワーク・照明・音声のディレクションから、
必要に応じてドローン撮影なども組み合わせ、
表現力の高い映像を実現します。
また、生成AIを活用した台本制作・構成設計・SNS投稿文作成・分析自動化など、
AIによる効率化と創造性の両立を実現。
**「AI × 映像 × 集客設計」**の掛け合わせで、
これまでにない成果型の映像マーケティングを提供しています。
これまでに登録者150万人超のYouTubeビジネスチャンネル立ち上げに参画。
戦略構築・演出ディレクション・改善分析を担当し、
視聴維持率・エンゲージメント向上に貢献しました。
Yahoo!広告認定資格を保有し、10年以上の広告運用経験から、
**流行に左右されない「持続的な集客導線」**を設計します。
今の時代、動画は「映える」ためではなく、「動かす」ために使うもの。
データ・AI・映像表現を融合し、
企業の想いを“伝わるストーリー”として形にするパートナーであり続けます。
最新の投稿
 AI2025年11月29日AI時代に必須のスキル!成果を出すプロンプトの書き方【初心者向け基礎講座】
AI2025年11月29日AI時代に必須のスキル!成果を出すプロンプトの書き方【初心者向け基礎講座】 AI2025年11月11日【AI時代の集客術】GEOとSEOの違いとは?中小企業が今すぐすべき対策を徹底解説
AI2025年11月11日【AI時代の集客術】GEOとSEOの違いとは?中小企業が今すぐすべき対策を徹底解説 AI2025年11月1日YouTubeサムネイルイラスト用プロンプト完全ガイド
AI2025年11月1日YouTubeサムネイルイラスト用プロンプト完全ガイド AI2025年10月30日世界で使われるYouTube台本フォーミュラ10選
AI2025年10月30日世界で使われるYouTube台本フォーミュラ10選
LINEからのお問合せ
LINEからご予約の場合、下記内容をお書き添えくださいませ。
動画(撮影・編集・YouTube)に関すること
マーケティングやAIプロンプト設計 に関するご相談も承っております。
「オリジナルのChatGPTプロンプトを作りたい」「AI活用をビジネスに取り入れたい」なども、お気軽にご相談ください。
- あなたの現在の状態をできるだけ詳しくお聞かせください
- あなたのご要望を教えてください
- オンライン相談ご希望の有無
このほか マーケティング に関するあらゆるご相談も承っております。
\ 私が担当いたします /
代表 松井 要
14年以上のデジタルマーケティング経験を持ち、これまで多数の業界で成果を上げてきました。
350万人超の登録者を誇るYouTubeビジネスチャンネルの立ち上げにも参画し、戦略設計から運用まで幅広く支援。広告運用やSEO・MEO対策を通じて、多くのクライアントの集客課題を解決してきました。
現在は、映像制作やドローン空撮を活用したPR・集客支援にも注力。特に、インタビュー動画や施設紹介映像など「伝わるストーリー設計」によるブランディング支援を得意としています。
さらに、AIを活用したデータドリブンなマーケティング施策にも対応。業界や流行に左右されない、持続可能で成果の出る集客戦略をご提案します。
問い合わせフォームがいい人はこちらから